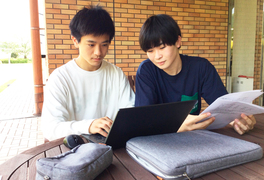鹿児島国際大学で学んでみませんか?
鹿児島国際大学はこんな学校です
鹿児島国際大学は学ぶ内容・カリキュラムが魅力

AIスキルもバッチリ 学部横断プログラムで深い学び
学びのスタイルに応じて、広い視野と実践力を有する人材を養成する「学部横断プログラム」を設置。「データサイエンス・AIプログラム」では、高度情報化社会において文理を問わず求められるデータサイエンス・AIへの関心を高め、活用する基礎的な能力を育成するために、それに関する知識と技術を総合的に学びます。そのほかには「公共経済プログラム」「金融経済プログラム」「鹿児島プログラム」「メンタルヘルスプログラム」を設け、多様で深い学びを提供します。
鹿児島国際大学は学外の人との交流が盛ん

地域に暮らす人々の生活を生涯支え続けるための人材を育成
経済・福祉・教育・芸術・看護等、地域の暮らしと密接に関わる学問分野を擁する本学では、地域が抱える課題を解決し、地域のさらなる活性化を担うことのできる人材の育成に取り組んでいます。講義で学んだ知識を活かしながら学外で活動する「フィールドワーク活動」では、地域課題に取り組み、解決策を提案。内容は、家庭で使い切れない未使用食品を集め、子ども食堂へ寄附するフードドライブ活動や、地域資源を活用するプランの提案など多岐にわたります。市町村や企業との協働を通じて課題の発見・解決力、行動力、コミュニケーション力などを育成し、社会で求められる実践的スキルに磨きをかけていきます。
鹿児島国際大学は自然がいっぱいの広いキャンパス

2023年4月に看護学部が開設され、2キャンパス体制に
坂之上キャンパスは、鹿児島中央駅から坂之上駅までJRで20分という立地に加え、南九州エリアでも有数の広さを誇っています。その広さは高校野球の全国大会で有名な「阪神甲子園球場」の5個分。緑豊かなキャンパスでは、自分のペースで落ち着いて学ぶには最適の環境です。看護学部が設置されている伊敷キャンパスは、鹿児島の中心街にアクセスしやすく、最寄りのバス停から徒歩5分の場所にあります。また、静かで学習しやすい文教地区に位置しているのが特長です。
あなたは何を学びたい?
鹿児島国際大学の学部学科、コース紹介
鹿児島国際大学の評判や口コミは?
在校生の声が届いています
-

-

多彩な業界で使える経済の仕組みを学び、就職の選択肢を広げたい。
- 経済学部 経済学科
-

社会福祉士と介護福祉士、ダブル資格取得を目指して介護のプロに!
- 福祉社会学部 社会福祉学科 介護福祉士課程
鹿児島国際大学の卒業後のキャリアや就職先は?
卒業生の声が届いています
-

「その人らしさ」を大切に。利用者様のよき理解者となり、感謝される支援を目指したい
- 福祉社会学部社会福祉学科介護福祉士課程 卒
- 社会福祉士(ソーシャルワーカー)
鹿児島国際大学の就職・資格
鹿児島国際大学の卒業後の進路データ (2023年3月卒業生実績)
卒業者数578名
就職希望者数512名
就職者数503名
就職率98.2%(就職者数/就職希望者数)
進学者数20名
充実した就職・キャリアサポート
「国内/海外インターンシップ」「3日間社長のカバン持ち体験」といった働く現場に立てる就職体験プログラムを用意。本格的な就職活動が始まる3年生では、個々の進路相談や大学主催の合同企業説明会、講座を通じて、実践的な就職活動の心構えを確立します。また、求人情報ファイル等が用意されている資料コーナーや、就職情報収集用のパソコンが設置され、さまざまな情報が入手できるようになっています。「やりたい仕事」という大きな目標を見つける・かなえるためにバックアップします。
鹿児島国際大学の所在地・アクセス
| 所在地 | アクセス | 地図・路線案内 |
|---|---|---|
| 坂之上キャンパス : 鹿児島県鹿児島市坂之上8-34-1 |
JR「鹿児島中央」駅から指宿枕崎線「坂之上」下車(乗車時間約20分)、無料スクールバス5分。 |
|
| 伊敷キャンパス : 鹿児島県鹿児島市下伊敷1ー52-17 |
JR「鹿児島中央」駅より鹿児島市営バス等(約15分乗車)にて「下伊敷」下車 徒歩5分 |
|
鹿児島国際大学で学ぶイメージは沸きましたか?
つぎは気になる学費や入試情報をみてみましょう
鹿児島国際大学の学費や入学金は?
初年度納入金をみてみよう
2024年度納入金/◎経済学部109万7660円 ◎福祉社会学部110万7660円 ◎国際文化学部109万7660円(音楽学科は164万2660円) ◎看護学部179万1660円 ※入学金及び学友会などの委託徴収費を含む ※福祉社会学部は学会費1万円(4年分)を含む
鹿児島国際大学の入試科目や日程は?
入試種別でみてみよう
下記は全学部の入試情報をもとに表出しております。
-
鹿児島国際大学の総合型選抜
総合型選抜をすべて見る試験実施数 エントリー・出願期間 試験日 検定料 20 9/15〜3/10 10/21〜3/14 30,000円 -
鹿児島国際大学の学校推薦型選抜
学校推薦型選抜をすべて見る試験実施数 出願期間 試験日 検定料 22 9/20〜12/6 10/21〜12/16 30,000円 -
鹿児島国際大学の一般選抜
一般選抜をすべて見る試験実施数 出願期間 試験日 検定料 8 1/5〜1/25 2/7 入試詳細ページをご覧ください。 -
鹿児島国際大学の共通テスト
共通テストをすべて見る試験実施数 出願期間 試験日 検定料 16 1/5〜3/10 1/13〜3/14 15,000円
合格難易度
鹿児島国際大学の入試難易度は?
偏差値・入試難易度
鹿児島国際大学の学部別偏差値・共通テスト得点率
鹿児島国際大学の関連ニュース
鹿児島国際大学に関する問い合わせ先
入試・広報課
〒891-0197 鹿児島県鹿児島市坂之上8-34-1
TEL:099-261-3211
(代)