別府大学で学んでみませんか?
別府大学はこんな学校です
別府大学は学ぶ内容・カリキュラムが魅力

国語の教員については新卒者の連続現役合格実績が11年連続となっています
本学では各学科に教職課程を設けており、関連する教科・科目の教員免許状を取得することができます。中でも「国語」の教員については、2012年度から11年連続で新規卒業者の正規採用実績が続いています。所定の単位を修得するだけではなく、専門教員による採用試験に向けた合格対策講座をはじめ、全学での取り組みとして行われる1~3年次生を対象とした「公務員試験受験対策講座」や、面接試験対策の「面接指導」や「スーツ着こなし講座」、「メイクアップ講座」等でも憧れの教職を目指す学生を支えています。(2022年度合格者数4名 2023年3月卒業生実績)
別府大学は就職に強い
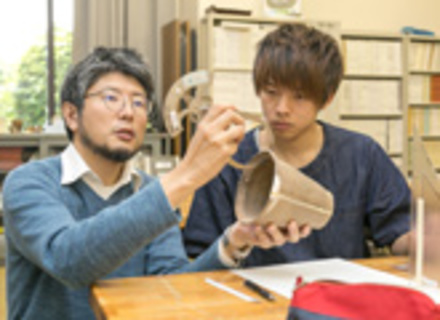
文化財関係専門職員には過去10年間で120名以上が合格しています
各県の県庁や教育庁、市町村の教育委員会等で採用となる「文化財関係専門職」。通常の公務員試験とは別の専門試験で採用される歴史・文化財分野に特化した公務員です。本学はこの文化財関係専門職員への採用実績が西日本でもトップクラスで、過去10年の採用実績だけで見ても120名の合格があります。業界における本学卒業生の占める割合は、九州内では32%、全国で見ても7%と高いものになっています。また、文部科学省によるブランディング事業にも採択されており、通常文学部では使用することのない最新の科学分析装置や測量機器が導入され、それらを学生が使用することができる環境が整っています。(2022年度合格者数17名2023年3月卒業生実績)
別府大学は施設・設備が充実

貴重な史料を収蔵する附属博物館をはじめ、地域文化の継承・発展を担う本学関連施設
本学の附属博物館は、学芸員を目指す学生にとって具体的な知識と技術を身につける実践の場となっているほか、学外の研究者や地域の人々の生涯学習の場としても一般開放されています。また、本学に附設されている「大分香りの博物館」では、世界の女性を魅了し続ける“シャネルNo.5”をはじめ、古代から現代に至るまでの香水を展示し、その歴史をわかりやすく鑑賞できるようになっています。さらに、発酵食品学科教員と連携した「香りと食の文化講座」なども開催され、地域文化振興の拠点として大きな関心が寄せられています。
あなたは何を学びたい?
別府大学の学部学科、コース紹介
別府大学の就職・資格
別府大学の卒業後の進路データ (2023年3月卒業生実績)
就職希望者数391名
就職者数374名
就職率95.7%(就職者数/就職希望者数)
進学者数20名
一人ひとりの自己実現を図るキャリア支援
大学は社会への出口と言われますが、4年間の大学生活は、これから一生「社会人」として自立し、社会に貢献しながら自分らしく人生をおくる「社会生活」への扉を開く力をつける時間でもあります。単に卒業して就職すれば良いというのではなく、自分にとって「なりたい自分」になるための将来を見据えたキャリアプランを立てることが大切です。一人ひとりの自己実現を図るために必要な人間力をつけるため、授業はもちろんのこと、キャリア教育科目を充実させ、社会で必要とされるコミュニケーション能力や問題解決能力等を身につけるとともに、キャリア支援センターを中心として、情報提供や進路対策事業等、全学で学生の支援に取り組んでいます。
気になったらまずは、別府大学のオープンキャンパスにいってみよう
別府大学のイベント
-

文学部...
【1日のスケジュール】 ▼受付開始 ▼学科セミナー ▼保護者説明会 ▼学生寮見学(希望者のみ) ▼入試個別相談コーナー ●別府大学へのご案内 ※運行内容が変更される場合がありますので、事前に運行状況をご確認ください。 ・JR利用の場合(最寄り駅は別府大学駅) ◎JR日豊本線別府大学駅から徒歩10分 特急利用の場合は、JR日豊本線別府駅下車、上りの普通 電車に乗り換え、4分で別府大学駅に着きます。 ・バス利用の場合 ◎JR日豊本線別府駅から(所要時間約20分) 亀の井バス〈別府大学経由鉄輪行〉「別府大学前」で下車 亀の井バス〈石垣経由国立別府病院行〉「別府大学下」で下車し、徒歩3分 大分交通〈石垣経由亀川駅行〉「別府大学下」で下車し、徒歩3分 ◎天神、JR博多駅、福岡空港から(所要時間約2時間半) 高速バスとよのくに号〈ノンストップもしくは各停〉「鉄輪口」で下車し、徒歩20分 詳細・お申込みはコチラをご覧ください。 https://www.beppu-u.ac.jp/exam/oc/
別府大学の所在地・アクセス
| 所在地 | アクセス | 地図・路線案内 |
|---|---|---|
| 別府 : 大分県別府市北石垣82 |
「別府(大分県)」駅からバス 25分 別府大学前下車 0分 「別府大学」駅から徒歩 10分 |
|
別府大学で学ぶイメージは沸きましたか?
つぎは気になる学費や入試情報をみてみましょう
別府大学の学費や入学金は?
初年度納入金をみてみよう
2024年度納入金:【文学部・国際経営学部】112万円 【食物栄養科学部】132万円(入学金・授業料・教育研究料含む)
別府大学の入試難易度は?
偏差値・入試難易度
別府大学の学部別偏差値・共通テスト得点率
別府大学の関連ニュース
別府大学に関する問い合わせ先
入試広報課
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
TEL:0977-66-9666














