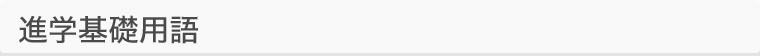講義
高校でいう「授業」のこと。通常、1講義は90 分。一般に、先生が教室の壇上で説明し、学生がノートを取る形式の授業をさす。ほかの授業の形式としては、ゼミや実習、フィールドワークなどがある。
ゼミ
数人から十数人の学生と先生によって構成される、学生の自主的な取り組みによって成り立つ大学・短大の授業のこと。先生はテーマを与え、研究を見守る助言者的存在であり、あくまでも授業を引っ張るのは学生。積極的な発言や討論に重点がおかれる。大学では3 〜4年次から設定される場合が多い。また、理系はゼミではなく研究室に所属し、専門分野を研究することになる。
実習
実践的な体験を通じて、講義で学んだことをさらに深める授業のこと。調理、美容など、職場と同様の設備を備えた実習室を使って行われるものが中心。ほかにも、決められたテーマについての共同作業を通じてお互いに学び合うワークショップ形式、教育実習(教員免許を取るために必須の実習)など実際の職場で実施する場合もある。専門学校では、仕事にすぐに役立つ専門技術を訓練する場として多くの時間が組まれる場合が多い。
フィールドワーク
授業の一環として、学外に出て行う実習の一種。例えば、教室で学んだ理論の裏づけをとるために、学外でのアンケートやインタビュー、調査を行ったりする。学んだことがどのように仕事や社会生活につながるかを考える機会にもなる。
専攻
専門的に研究する学問分野のこと。大学・短大では、1年次などの早い時期に、英語や憲法などの一般教養科目の単位を取り、その後(1年次の後半か、2次が多い)、それぞれの専攻に分かれて専門分野を学ぶ。 また、専門学校では、1年次から専攻が決まる学校が多いが、なかには複数の類似分野を同時に学び、2年次以降専攻を選べるといった学校もある。
併修
専門学校に通いながら、大学・短大の卒業資格を得ることを目指す制度。専門学校の学科、コースや併修の内容により異なるが、専門学校に在籍すると同時に、大学・短大の通信教育課程に入学して、課程修了後に「学士」「短期大学士」の学位取得ができる。受験できる資格の幅が広がるなどのメリットがある。
単位互換
ほかの大学・短大などで授業を受け修得した単位が、一定限度まで在学中の学校の単位として認められる制度(学校間で協定がある場合)。留学先の大学で取った単位を認め、「1年間留学しても、留年せずに卒業できる」制度をもつ学校などもある。短期間で様々なテーマを学べたり、異なる学校での学びを体験できるメリットがある。
卒業論文(卒論)
主に大学・短大で、担当の先生の指導を受けながら卒業するために書く、専攻分野に特化したテーマで書く論文のこと。学びのまとめとして、知識、実験結果、考えなどをまとめることで、深い研究成果をあげることを目指す。学校、学部、学科などによって、書かなくても卒業できる場合もある。