オンライン
開催イベント
万葉挽歌の表現 ~挽歌とはなにか~
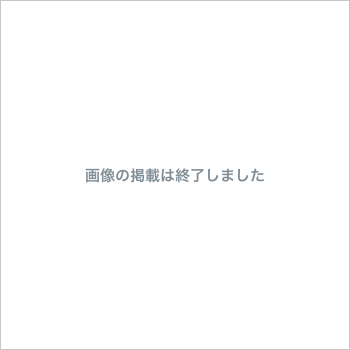
- 開催日時
-
-
2024年3月9日(土)14:00~15:30
-
申込URL:https://www.ou.tmu.ac.jp/web/course/detail/2341Z006/
※本講座はオンライン講座でライブ+見逃し配信で7日間何度でも視聴可。
古より、死は人間が免れ得ない事柄の一つでした。身近な者の死、敬愛する者の死、やがて訪れる自己の死を、どのように認め克服していくのかが、文学に託された一つの課題であったともいえます。平安時代から現代に至るまで、日本人の死葬儀礼や死生観に深く結びついてきたのは主に仏教です。しかし、それ以前の上代には、人々の脳裏に仏教が浸透する以前の古い死生観に基づく儀礼がとり行われ、それらを反映する神話や歴史叙述、歌謡や和歌が記されました。
現存する我が国最古の和歌集『万葉集』にも、人の死に関わる多くの歌が収載されています。『万葉集』は雑歌・相聞・挽歌という三大部立を基本構造として持ち、人の死に関わる歌は主に挽歌の部に収められています。つまり『万葉集』に於ける挽歌は、天皇や宮廷に関わる公的儀礼歌である雑歌や、恋の歌である相聞と並ぶ重要な位置を占めていたのです。ここから、当時の人々が死や死葬文化をいかに重視していたかが分かります。平安時代以降の勅撰和歌集では、人の死に関わる歌は哀傷(または哀傷歌)の部に収められ、もう挽歌という部立名は使われなくなります。挽歌は数多の和歌集のうち『万葉集』だけにしか見えない呼称なのです。
それでは、挽歌とはどのような歌なのでしょうか。当時の人々は「死」という概念をどのように捉えていたのでしょうか。彼らはどのように死と向き合い、死者に思いをはせたのでしょうか。挽歌に於いて、この世を去った死者はどこへ向かうと幻想されたのでしょうか。
本講座では、万葉第二期に活躍し多くの挽歌を詠じて「挽歌歌人」とも称される柿本人麻呂が、女性の死を悼んだ挽歌作品をいくつか取り上げ、その表現を読み解くことで、当時の人々の思いや死生観、他界観に迫ってみたいと思います。
講師 東京都立大学 人文社会学部 准教授 高桑 枝実子
※本講座はオンライン講座でライブ+見逃し配信で7日間何度でも視聴可。
古より、死は人間が免れ得ない事柄の一つでした。身近な者の死、敬愛する者の死、やがて訪れる自己の死を、どのように認め克服していくのかが、文学に託された一つの課題であったともいえます。平安時代から現代に至るまで、日本人の死葬儀礼や死生観に深く結びついてきたのは主に仏教です。しかし、それ以前の上代には、人々の脳裏に仏教が浸透する以前の古い死生観に基づく儀礼がとり行われ、それらを反映する神話や歴史叙述、歌謡や和歌が記されました。
現存する我が国最古の和歌集『万葉集』にも、人の死に関わる多くの歌が収載されています。『万葉集』は雑歌・相聞・挽歌という三大部立を基本構造として持ち、人の死に関わる歌は主に挽歌の部に収められています。つまり『万葉集』に於ける挽歌は、天皇や宮廷に関わる公的儀礼歌である雑歌や、恋の歌である相聞と並ぶ重要な位置を占めていたのです。ここから、当時の人々が死や死葬文化をいかに重視していたかが分かります。平安時代以降の勅撰和歌集では、人の死に関わる歌は哀傷(または哀傷歌)の部に収められ、もう挽歌という部立名は使われなくなります。挽歌は数多の和歌集のうち『万葉集』だけにしか見えない呼称なのです。
それでは、挽歌とはどのような歌なのでしょうか。当時の人々は「死」という概念をどのように捉えていたのでしょうか。彼らはどのように死と向き合い、死者に思いをはせたのでしょうか。挽歌に於いて、この世を去った死者はどこへ向かうと幻想されたのでしょうか。
本講座では、万葉第二期に活躍し多くの挽歌を詠じて「挽歌歌人」とも称される柿本人麻呂が、女性の死を悼んだ挽歌作品をいくつか取り上げ、その表現を読み解くことで、当時の人々の思いや死生観、他界観に迫ってみたいと思います。
講師 東京都立大学 人文社会学部 准教授 高桑 枝実子








