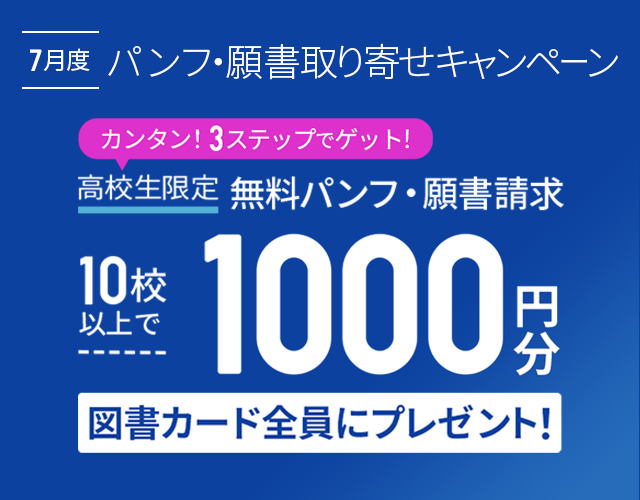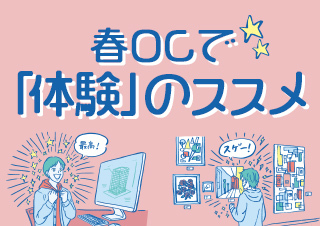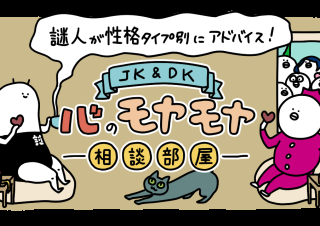一夜漬けの暗記のコツは?東大生がテスト前の効果的な勉強法を伝授!
テストや模試の前日なのに、気が付けば勉強が全く終わっていない!こうなったら一夜漬けするしかない!?そんな経験がある人もいるのでは?
そこで、現役の東大生・東大院生、東大卒業生にアンケート。
効果的な一夜漬けのコツを聞いてみた!
資格研究家で短期学習のプロ、鈴木さんのアドバイスも参考にしよう。
目次
- 東大生に聞いた!一夜漬けってどうなの?
- 東大生が教える!一夜漬け成功のコツ8
- 1.全体を俯瞰してやるべきポイントを探る
- 2.授業のノートを徹底活用する
- 3.要点や弱点のまとめメモを作る
- 4.暗記事項の定着のために、書いて覚える
- 5.ヤマをかける・出題者側の立場で考える
- 6.難しい問題には手を出さずに、基礎を理解する
- 7.教科にかける時間や休み時間の配分を意識する
- 8.集中力アップのために音楽を活用する
- 【科目別】東大生が教える!一夜漬けの暗記法
- 【国語】の一夜漬けは漢字や古語など語彙の暗記を優先させる
- 【英語】の一夜漬けは英単語やイディオムの暗記を重点的に行う
- 【社会】の一夜漬けは歴史の流れ、位置関係、関連性をおさえる
- 【数学】の一夜漬けは公式を暗記して基礎的な問題を繰り返し解く
- 【理科】の一夜漬けは効率の良い暗記分野を集中的に行う
- 東大生に聞いた!一夜漬けするときの注意点
- 一夜漬けする高校生へ、東大生&プロからアドバイス

鈴木秀明(すずきひであき)さん
1981年8月4日富山県生まれ。
東京大学理学部、東京大学公共政策大学院を経て、2006年4月より某人材会社に入社。
2009年に退職後、資格・勉強法アドバイザーとして独立。
総合情報サイトAll About 「資格」ガイド。(https://allabout.co.jp/gm/gp/398/)
年間80個ペースで資格・検定試験を受け続ける資格マニア。
2023年7月時点で約900個の資格をすべて独学で取得している。
雑誌・テレビ・ラジオなどのメディア出演実績は500件超。
東大生に聞いた!一夜漬けってどうなの?

※一夜漬けのメリットデメリットについて東大生はどう考えているだろうか
東大生からは、一夜漬けは暗記系の追い込みには有効だという意見も一定数あった。またテスト前日という緊張感が集中力をアップさせる効果もあるのではという声も挙がっていた。
しかし、前日の暗記だけだと、どうしても短期的な記憶にしかならないという意見が多数。
時間が経つと忘れてしまうというデメリットについて、多くの人が警告しているようだ。
では、一夜漬けのメリットデメリットについて、詳しく見てみることにしよう。
一夜漬けのメリットは、暗記の記憶が残っているうちにテストを受けられること
「短期記憶が得意なので前日にいか詰め込むかで点数が変わる」 (29歳・総合文化研究科)
「暗記系は直前までできるだけ覚えた方がいいと思う」(23歳・新領域創成科学研究科)
「簡単な暗記問題なら有効」(20歳・教養学部)
「集中できるし、短期記憶で覚えたことをすぐに発揮できる」(21歳・法学部)
「短期記憶が効くので、テストである程度の点が効率良く取れる」(23歳・工学系研究科)
●集中力が高まった状態を作り出せる
「高強度の思考で新たな発見をもたらす可能性がある」(年齢未回答・新領域創成科学研究科)
「一夜漬けでは、いざやらねば、という一種の過集中状態に入るので、そのアドレナリン全開の状態で勉強することはこのうえない充実感につながり、それは試験を受ける上での最大の火薬に」(20歳・文学部)
「最後の追い込みということで気合が入る」(20歳・教養学部 理科一類)
「点数を取るうえでの対時間効果がとても大きい」(19歳・教養学部)
一夜漬けのデメリットは、暗記した記憶が定着しづらいこと
「本質理解につながらないからあまり良くないと思う」(24歳・法学政治学研究科)
「記憶が定着しない。テストだけを乗り越えるのに尽きてしまう」(20歳・理学部)
「一夜漬け自体が大変だし、長期記憶にはつながらない」(23歳・工学系研究科)
でも、やるとなったらあまり思い詰めないでほしいですね。
受験という長期的な目標に向かって勉強していると、どこかでだれてきたり、スランプに陥ったりしますよね。
試験前日という独特な状況だと、普段できないことができることもある。
そんな緊迫した状態のときに集中して学習することで、思いがけずスランプを脱することができたりもします。
一夜漬けで詰め込んだ勉強内容をそれきりで放置するのでは、残念ながら学習効果を得るのは難しいでしょう。
しかし集中的に学習した内容を、テストの後でしっかり復習すれば、定着させることもできるのです。(鈴木さん)
東大生が教える!一夜漬け成功のコツ8

※少しでも効率的に行うために東大生のアドバイスを聞いてみよう
一夜漬けのコツは無暗に学習の手を広げないことだと、東大生の多くが指摘する。まず教科書や授業ノートを使って全体を俯瞰し、効率よく学習しよう。
1.全体を俯瞰してやるべきポイントを探る
東大生のなかには、短い時間での学習効率を上げるため、試験範囲の内容を俯瞰して、試験に出そうな箇所や自分が苦手な個所を割り出して臨む人が多かった。「全体をざっくりとさらって忘れてるとこがないかを確認」(20歳・教養学部)
「教科書、ノートで試験範囲全体を確認する。理解しきれていない箇所や難易度の高い問題を重点的に見直す」(20歳・教養学部 理科一類)
2.授業のノートを徹底活用する
それまで学習に手を付けていなくても、授業はまじめに受けている人が多数。そのノートを武器に学習をすると、得点効率が良いようだ。
「ノートを見返して先生がやたらと強調していたところマークがついているところを重点的に勉強する。授業中、課題としてやった演習問題は暗記ゲームのように覚える」(20歳・文学部)
「授業ノートや教科書などで、先生が重点的に言っていた箇所についてさらう。暗記分野の確認」(21歳・法学部)
「ノートの確認。(授業内だけでノートを完璧に取っておく必要はある)」(24歳・農学生命科学研究科)
3.要点や弱点のまとめメモを作る
広い試験範囲の全てを、一夜漬けで完璧に学習することはできない。だからやるべき要点や苦手箇所をまとめて、それだけは確実に頭に残るようにすると、試験で使える知識になる。
「夜に暗記科目をして朝にもう一度見直す。 苦手な部分は紙にまとめて1日に何度も見直す」(19歳・教養学部)
「わからないところだけ小さいメモに書く」(18歳・教養学部)
「間違った問題だけを書き出したノートや、引っかかりそうだと思う場所を再チェックする」(18歳・教養学部)
4.暗記事項の定着のために、書いて覚える
記憶の定着のために、手を使って書いて覚えることが有効だというアドバイスが多数あった。「英単語をひたすら書いて覚える」(19歳・教養学部)
「漢字は覚えれば確実に得点になるので、書いて完璧に覚える。対義語や語句の意味なども暗記すれば得点源に」(34歳・教育学部)
「アウトプットする。白紙に書き出すなど」(20歳・理学部)
5.ヤマをかける・出題者側の立場で考える

※授業中の先生の発言や板書からテストに出題されそうなことを見つけよう
出題者の傾向を分析して、ヤマをかけることも、多くの東大生が行っていた技。先生の普段の授業や過去問題の出題傾向から分析している。
「過去問で傾向がわかるなら、出そうなとこの暗記、文章の読み直しをする」(20歳・法学部)
「社会系の科目は出題者側の立場に立ち、ここはこう出題できそうだなと考えたり、単語に対して頭の中で率直な感想を述べたりして暗記しやすくした」(18歳・教養学部)
6.難しい問題には手を出さずに、基礎を理解する
事前の勉強が足りず一夜漬けになってしまった場合は、難しい問題や細かすぎる事項には手を出さず、基礎を理解することに時間を割くほうが良いというアドバイスがあった。「問題等を丸覚えしたり、焦りすぎること。少しでも、ゆっくりでも基礎を理解するほうが大事」(20歳・教養学部 理科一類)
「基礎だけを押さえるつもりで教科書を見直す」(26歳・理学系研究科)
7.教科にかける時間や休み時間の配分を意識する
限られた時間で最大限の効果を上げなければいけない一夜漬け。タイマーでスケジュールをコントロールしながら勉強すると効果的だそうだ。
「25分やって5分休憩するなど、自分なりの勉強のペースを決めるとよい」(21歳・法学部)
「残り時間でやれることに優先順位をつける」(21歳・法学部)
8.集中力アップのために音楽を活用する
集中力を高めるために音楽を活用するという意見も。人によって合う・合わないがある方法だが、音楽によって集中力が増す人もいる。
「好きな音楽をかけると集中できるので、いつもかけていました。深夜に及ぶ時はリポビタンDのような栄養ドリンクを飲んでいました」(20歳・工学部)
「あの音楽を聴いてた時に見たな、と記憶が結びつくことも多い」(24歳・農学生命科学研究科)
「音楽は外部の音を遮断できる分、人によっては集中できる」(19歳・教養学部)
さまざまなコツがあったが、鈴木さんの意見も聞いてみよう。
ですから「全体を俯瞰してやるべきポイントを探る」というのは大事です。
また、「ヤマをかける・出題者側の立場で考える」というのも能動的に学習をするために大切なポイント。
一方で、「書いて覚える」のはある程度勉強する範囲が絞れている場合は良いのですが、覚えなければならないことをすべて書いていては、時間が足りない場合もあるでしょう。
そういった場合は、重要なポイントや試験に出そうな部分だけに集中して頭に叩き込むようにしましょう。
「要点や弱点のまとめを作る」というのも同じで、イチからまとめを作っていたのでは時間がない。
本当に重要な部分や、試験前日にどうしても覚えられなかった弱点だけを、試験本番直前に見直せるように厳選してまとめることが大切です。
テスト前にするべきことは、それまでの学習の到達度によって違います。
ノートをきちんと取っているか、授業ぐらいはしっかり聞いていたかでも違うでしょう。
さまざまなコツのなかで自分の状況に合ったものを取り入れると良いですね。(鈴木さん)
【科目別】東大生が教える!一夜漬けの暗記法

※一夜漬けで暗記するにはどうするのが効果的?
一夜漬けの学習では、暗記モノの学習効率が高いと、多くの東大生が指摘している。しかし暗記といっても、その内容や最適な方法は科目ごとに違うはず。
そこで東大生にそれぞれの科目の効果的な暗記法を教えてもらった。
【国語】の一夜漬けは漢字や古語など語彙の暗記を優先させる
国語の暗記事項で多くの人が挙げていたのが、漢字や古語などの言葉の暗記だ。また古文や漢文で、出題される文章が決まっている場合は、その現代語訳を暗記しておくと読解に役立つ。
「漢字を書けるか確認して当日の朝に書けなかったものを再確認する」(20歳・教養学部)
「手っ取り早く点が取れる、漢字や古文・漢文の単語の意味を暗記する」(28歳・教育学部)
「先生が授業で述べた文法ポイントなどについて重点的に復習する」(21歳・法学部)
「古文の助動詞の活用と意味を徹底的に叩き込む」(23歳・法学部)
「古文の枕言葉を覚える」(32歳・学部未回答)
「古文なら何も見ずに文法的説明や現代語訳ができるようにする」(24歳・人文社会系研究科)
「テスト範囲の文章、授業中のノートを一通り読んでおく」(27歳・法学部)
【英語】の一夜漬けは英単語やイディオムの暗記を重点的に行う
英語は単語やイディオムを知らないと文章が読めないので、試験範囲のものはしっかりと覚えよう。読みと綴りを結びつける音読も効果的だ。
「単語やフレーズは、実際に声に出してリズムで覚える。同時にノートにスペルを書き、目と耳の両方で記憶させる」(34歳・教育学部)
「単語帳を丸暗記してもダメ。それよりも、文章を読む中でわからない単語の意味を覚えるほうがいい」(39歳・文学部)
「試験範囲のちょっと変わった文を覚えておく。代名詞が何を指すのか知っておく。文法を理解しておく」(36歳・工学部)
「文法問題は知らないとどうにもならないので、理解しておく。単語ばかりを詰め込んで、大まかな意味がわかっても問題が解けないことが多い」(24歳・工学部)
「試験範囲の英単語は100パーセントになるまで覚えておこう。教科書の文章も予め暗誦しておくと良い」(20歳・文学部)
単語だけを抜き出して暗記するより、文章の中で文法やイディオムと合わせて覚えたほうが記憶に残りやすく、使える英語になるようだ。
「ざっくり覚えて満足するのはダメ! ちゃんと正しいスペルで書けるようにする」(34歳・工学部)
「何となく教科書を眺めるのはNG」(34歳・農学部)
【社会】の一夜漬けは歴史の流れ、位置関係、関連性をおさえる
社会は暗記物が多く一夜漬けでも比較的得点しやすい科目だ。細切れではなく、地理なら位置関係、歴史なら同時代の他の出来事との関係性を意識しつつ暗記すると、知識が定着しやすい。
「教科書の流れを把握する」(20歳・工学部)
「歴史なら時の支配者等人名を覚えてまず時間軸を作る。その上で細かい部分を覚える」(21歳・教育学部)
「ノートの確認をする。(ただし、授業内だけでノートを完璧に取っておく必要はある)」(24歳・農学生命科学研究科)
「優先すべきは教科書の太字ないしノートの赤字。特に重要そうな出来事の年号は自身で語呂合わせなど作るなどして覚えるのが良い」(20歳・文学部)
「歴史の流れで覚える」(18歳・教養学部)
「関係などを白紙にすべて書き出す」(20歳・農学部)
「地理や公民は本当に覚えなければいけないことを見極めてそれだけ覚え、残りはひたすら資料集等を読む」(21歳・教育学部)
【数学】の一夜漬けは公式を暗記して基礎的な問題を繰り返し解く
数学は暗記だけで点を取ることが難しい分野だ。ただ公式を暗記するのではなく「公式を覚えてできるだけ多くの問題を解く」ことを意識しよう。
「まずは答えを見ながら解いて、解法の流れを覚える。公式だけを覚えても、結局どこで使うかが正しくわからないと意味がない」(24歳・工学部)
「一度解けなかった問題を解き直し、解説を読んですべて解けるようにする」(29歳・教育学部)
「公式とその使い方を徹底的に覚えて、例題レベルはできるようにする。量を解く時間はないので、解法を叩き込む」(21歳・教育学部)
「間違えやすい公式や苦手な問題を、理解して解けるようになるまで何度も問題集等で繰り返す。数学は苦手克服だけで点数がアップする」(34歳・教育学部)
「時間がない時は解法だけ確認する。具体的な計算は基本飛ばす」(24歳・人文社会系研究科)
「生理的に受け付けない、自分一人の頭では理解できないくらいのどうしてもわからないものは、いっそのこと潔くあきらめて捨てて、得意分野を増やす。できる問題で自信をつける方がいい」(34歳・教育学部)
【理科】の一夜漬けは効率の良い暗記分野を集中的に行う
理科は物理など計算が必要な分野と、生物などの暗記が多い分野が混在する。一夜漬けの効率が良いのは、やはり暗記系の分野だという意見が多数。
計算が必要な分野は公式を覚え、基礎的な問題を解くという、数学と似た学習法が効果的なようだ。
「時間が限られているなら、暗記が得点につながるものを優先したほうが効率的」(22歳・学部未回答)
「物理はまずは公式を覚え、何度も解き方を復習する」(29歳・学部未回答)
「暗記事項は、なるべく知識同士をつなげて覚える。覚えるべき量を厳選したうえで気合いで叩き込む(特に映像記憶がおすすめ)。計算問題はとにかく解法を叩き込む」(21歳・教育学部)
「授業用ノートをひたすら見て、計算や式変形などはできるようにしておく」(23歳・工学系研究科)
東大生のコメントを見ると、多くの人は効率の良い暗記の方法がわかっているようでした。
国語・英語など語句の暗記だったり、社会や理科の理論分野だったり、暗記で得点できる余地が大きい分野は、特に注力しましょう。
逆に数学や理科の計算分野は、ある程度の演習量が必要なので短期的な学習では効果が出にくいのですが、解法を暗記することはできます。
その際に、いちいち問題を解いていると時間がなくなってしまうので、解法のパターンのみを理解して、暗記するようにすると、思いのほか得点を伸ばせると思います。(鈴木さん)
東大生に聞いた!一夜漬けするときの注意点

※どうしても一夜漬けをしなければいけないとき、注意すべきことは?
ここまで、一夜漬けで可能な限り得点するための勉強法を紹介してきた。しかし、一夜漬けは心身共に負荷がかかるのは事実。
東大生に一夜漬けする際の注意点も聞いたので、耳を傾けてみよう。
ある程度の仮眠時間を確保しよう
仮眠時間に関する東大生へのアンケートでは、平均すると4時間の睡眠時間を取ることを推奨していた。試験中のコンディションに影響が出ないように、ある程度の睡眠時間が必要だという意見が圧倒的に多数だった。
「人間は寝ている間に記憶の整理を行うので、一夜漬けでも必ずいつもと同じ時間寝るのが良いと思う」(38歳・経済学部)
「勉強した後、1時間でもいいから寝る。寝る直前まで勉強はする」(34歳・教育学部)
「テストは連日続くため、1日を乗り越えればいいというものではなく、最低限の睡眠は取るべき」(19歳・教養学部)
寝る30分前「暗記のゴールデンタイム」を活用しよう
どれだけ睡眠時間を削って必死で勉強したとしても、記憶として定着しなければ意味がない。
人間は寝ているあいだに記憶の整理や定着を行うので、「一夜漬け」とはいっても、きちんと睡眠を取らないといけない。
ハーバード大学医学部精神科教授のロバート・スティックゴールド博士によると、新しい知識やスキルを身につけるには、学んだその日に6時間以上の睡眠を取る必要があるそう。
6時間以上眠ることによって、記憶が整理され、脳のあるべきところに収まるので、長期記憶として定着する。
反対に、徹夜をして十分な睡眠を取らなかった場合は、早ければ翌日には忘れてしまう。
記憶の定着と睡眠には密接な関係があることを覚えておこう。
効率良く暗記をするには、6時間以上の睡眠を取ることに加え、暗記学習のタイミングも大切。
寝る前に覚えたい情報をインプットしてすぐに眠ると、睡眠中に余計な情報が入らないため、寝る前の30分間は暗記のゴールデンタイム!
英単語などの「暗記もの」の勉強をすると効率よく暗記ができる。
勉強をした後にスマホを触ったり、ゲームをしたり、テレビを観たりすると、雑多な情報で脳が混乱してしまい、記憶の定着のさまたげになってしまう。
そのため、暗記学習の後はできるだけ余計なことをせず、すぐに寝てしまうといい。
効果的に暗記学習をしたい人は、寝る前30分間のゴールデンタイムを活用して、睡眠を味方に付けることを意識してみよう。
胃腸に負担をかけない食事を心がけよう
試験前夜の食事は、コンディションを左右するから重要だ。東大生のアンケートでは、胃腸の負担にならない食事を心がける人が多かった。
一方でここぞという時にはエナジードリンクやカフェインを活用していることもわかった。
「深夜に何かをつまむ程度はしていたが、基本的にはいつも通りだった」(23歳・工学系研究科)
「19時過ぎに夕食を食べた後は特に何も食べないが、24時ごろにコーヒーかエナジードリンクを飲んで気合いを入れる」(21歳・教育学部)
「夕食は野菜など糖分低めなものにする。そうすることで眠くならない」(21歳・法学部)
体調維持を一番に考えよう
最後に重要なことをひとつ言うと、多くの東大生が、一夜漬けで体調不良になることを心配していた。勉強は長期戦だ。一夜漬けをするにしても、身体に害がないように十分に気をつけよう。
「体調管理に気をつけて頑張ってください」(21歳・学部未回答)
「一夜漬けをするならば、体調を考えて無理をしないこと」(26歳・理学系研究科)
ただ、自分なりのペースがある程度わかっている人は無理に変えようとしないほうが良いと思います。
私はいつも集中力を高めるために、試験前はあまりものを食べない派なんですが、高校生は成長期なので、いつも通り食べたほうがよいと思いますね。
睡眠に関しても、きちんと取るのがベストではありますが、興奮して寝付けないというような場合は、「○時までには寝ないとまずいのに…」と過剰に心配するとかえって寝付けず逆効果になってしまうこともあります。
もし予定通りの時間に眠れなかったとしても、翌日にいつも通りの体調を保てているのなら、睡眠時間が短いことに対して過度にストレスを感じる必要はありません。
睡眠時間を削りすぎて、体調を崩してしまうようなことは絶対に避けるようにしましょう。(鈴木さん)
一夜漬けする高校生へ、東大生&プロからアドバイス

※最後まであきらめずに目標に向かって頑張ろう!
最後に、一夜漬けに挑もうとする高校生に東大生からアドバイスをもらった。今この瞬間、勉強に対してやる気になっているみんなへのエール、そして、今後は計画的に勉強して受験に備えてほしいという気持ちのこもったメッセージがたくさん届いている。
くれぐれも一夜漬けで勉強を終わらせず、今回のテスト分野は後で復習して受験に役立つ力にしよう!
「勉強しなかった分野で得点できないのは仕方がないので、テスト後に復習すればいい」(20歳・工学部)
「今まで勉強しなかったことへの後悔は後にして、ひとまず目の前の勉強に集中して頑張ってください!」(23歳・工学系研究科)
「一夜漬けをするときは、焦る気持ちもわかりますが、焦りすぎず、自分の苦手な箇所や公式等の重要な箇所に焦点を当てて効率的に勉強しましょう」(20歳・教養学部 理科一類)
「今勉強をしっかりするという経験は、希望の大学に合格するために勉強するときの自信につながると思うので、今後は一夜漬けに頼らずにコツコツと勉強しましょう」(18歳・教養学部)
一夜漬けをする、つまり短期間に集中して勉強すると自分はどのくらいのことができるのか、知っておくのもひとつの経験です。
ただ、くれぐれも無理はしすぎないことを心に留めてくださいね。(鈴木さん)
この苦しい状況のなか、みんなが少しでも前向きに頑張れるよう、いろいろな考え方や勉強法を伝えてきた。
明日のテストで1点でも高い点数が取れることを祈っているので、体調を崩さないように気をつけつつ、最後まであきらめずに頑張ろう!
そして、この経験を今後のテスト勉強や受験勉強に生かしていってほしいと思う。
取材・文/PlanB、蜂谷智子 監修/鈴木秀明 構成/スタディサプリ編集部
※本調査は2018年9月、2023年6月、東大生・東大院生・東大卒業生57名にアンケートを実施
★関連記事をCHECK!
東大生の1日の平均勉強時間は7.5時間。勉強時間を増やすコツは?現役生50名に聞いた!
東大生のおすすめ勉強法!受験期にやってよかったこと・失敗したことを現役生50名に聞いた!
東大生98人に聞いた!受験勉強っていつから、何をすればいい?
東大生98人に聞いた! 効率的に覚えられるオススメの暗記法