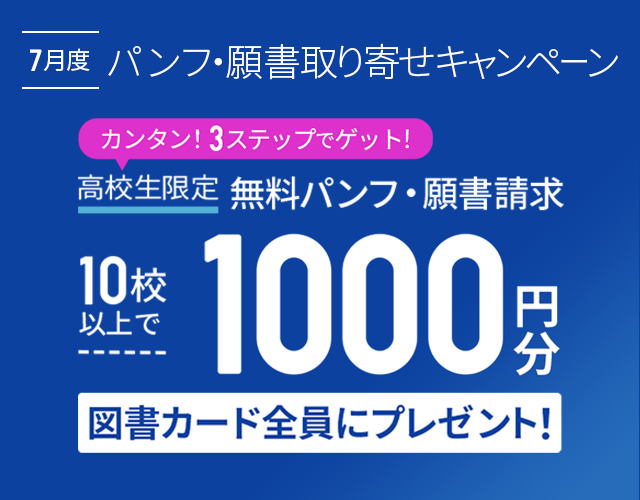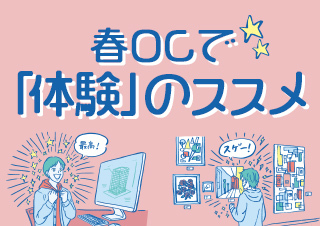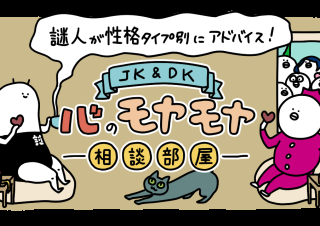探究学習って何?日常で心が揺さぶられることにヒントがある!?
高校での学び方が大きく変わっている今、「探究」に重点をおいた「探究学習」という授業がこれから増えてくる。
「探究学習」とは、これまでのように出題された問題に対し、1つの答えを誰かから教わるのではなく、自分で問いや課題をみつけて設定し、情報を収集・整理しながら、ほかの人と議論・協力して、自分独自の最適な答えを見つけていく学びのこと。
変化の大きいこれからの世の中で活躍するための、柔軟な発想力、自分とは違う意見や価値観を受け入れる力、新しいことに挑戦する行動力などが伸ばせると期待されている。
これからますます注目されていく「探究」だけど、「ちょっと難しそう…」「自由研究とか探究学習って苦手かも…」「何を調べたらいいの?」と戸惑っている人もいるのでは?
そこで今回は、NHKの人気番組『チコちゃんに叱られる!』の番組制作にかかわっているプロデューサーに、日常の疑問を拾って楽しく探究する様子を聞いてきた!

【プロフィール】
西ヶ谷力哉さん
株式会社NHKエンタープライズ
制作本部 情報文化番組
エグゼクティブ・プロデューサー
平成7年NHKに入局。ディレクターとして『プロジェクトX』などのドキュメンタリー、情報番組を制作。プロデューサーとして『あさイチ』『ファミリーヒストリー』『フランケンシュタインの誘惑』『チコちゃんに叱られる!』などを担当する。
★どんな番組を作っているの?

※雑学バラエティー『チコちゃんに叱られる!』
『チコちゃんに叱られる!』
NHK 総合 毎週金曜 午後7:57~8:42 ※一部地域では別番組放送
<再放送>毎週土曜 午前8:15~8:50 ※一部地域では別番組放送
「いってらっしゃーいってお別れするとき、手を振るのはなぜ?」
「かんぱーいってするときにグラスをカチン、あれはなぜするの?」
5歳のかわいい女の子、チコちゃんが次々に聞いてくる素朴な疑問の数々。
考えたこともないと答えられずにいると、チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねえよ!」と叱られてしまいます!
すぐに誰かに話したくなる情報満載の、今まで見たこともなかった雑学番組。
疑問や答えは身近なことほどハッとする!誰でもわかる言葉で伝えることが大事
どれもみんなが『確かに!』と共感する疑問だけど、どうやってみつけているの?
※『電車に乗ると眠くなるのはなぜ?』といった身近なことを題材にするとみんなの興味がわく
例えば、古語の『いとおかし』にまつわる疑問の答えがびっくりするおもしろいものだったとしても、その言葉を日常的に使っていなければハッとしません。
むしろ、『電車に乗ると眠くなるのはなぜ?』といった誰でも一度は経験があること、触ったり使ったりしたことのあるものなど、身近な題材のほうがハッとするんです。
そのほか、ディレクターが考えついたネタに、できるだけダメ出しをしないこともこだわりだと思います。
どんなネタでも、答えを探すために深掘りしていくとおもしろいエピソードが出てきて、『もっと詳しく調べてみよう』となることがよくあるんです。
また、難しい答えであっても、どうやってそれをかみ砕いて伝えるか、その工夫次第で、視聴者の皆さんをハッとさせることができることもあります」。
視聴者に伝えるときに、気をつけていることってある?
※『f分の1ゆらぎ』はお母さんの胎内にいた時に聞こえていた音に近いんだ!
「例えば、『電車に乗ると眠くなるのはなぜ?』という疑問の答えには、『f分の1ゆらぎ』というメカニズムが関係しているのですが、その専門用語を紹介しても身近な言葉ではないので、みんなピンとこない。
そこで、『f分の1ゆらぎ』についてもっとかみ砕いていくと、実は、電車の中で聞く音や感じる振動が、お母さんの胎内にいた時に聞こえていた音や感じていた振動に似ていて、守られている安心感から眠くなるということがわかってきたんです。
結局、専門家の先生と相談して番組では『f分の1ゆらぎ』という言葉を使わずに、『お母さんの“おなかの中”を思い出すから』というわかりやすい言葉で紹介しました。
そうやって詳しく調べたり、切り口を考えたり、専門家と議論したりしながら、質問と答えを考え、視聴者の皆さんに『なんで?』『そうなんだ!』とハッとしてもらえるような番組にしたいといつも考えています。」
難しい言葉って使いたくなっちゃうけど、人に伝えるときはその人に共感してもらえる言葉を使うことって大事なんだ!
答えがわからなくてもいい!?どこまでどう調べたかが大事!
ネタを決めるだけでなく、調べる過程もなかなか大変そう。
実は、調べても答えがわからなかったという回もあるんだそう!

※どうして左投げピッチャーのことを“サウスポー”というの?
まず、アメリカの野球場の向きから、左利きのピッチャーがマウンドに立ったときに左手が南側にくることが“サウスポー(南の手)”の由来なのではないかという答えにたどりつきました。
アメリカの歴史ある野球場は、太陽光がバッターの目に入らないように、ほぼほぼ同じ向きを向いているんです。
『それはおもしろい!』ということで、どのようにVTRを作成しようかと考え始めていたのですが、アメリカの野球についての専門書を見てみると、『その説は幻想』と書かれていたんです…!みんながっかりしてしまいました。
次にサウスポーの由来はボクシングなのではないかという説が取材によって浮上します。そこで、ボクシング協会に聞いたところ、今度は『野球場の向きが由来となった用語だと聞いている』と、スタートに戻るような返答が…。
もうみんなで頭を抱えてしまいました。
そして悩んだ結果、調べたすべての過程を視聴者の方に見せるようなストーリーにして、『結局、いろいろ調べたが、“サウスポー”の由来はわからなかった』というVTRを作りました。
スタジオと放送で、どのような反応が返ってくるか心配でしたが、とことん調べ、正しい知識を伝えること、わからないものをわからないと正直に伝えること、という姿勢を見せたことを好意的に受け取ってもらえたんです。
これは、うれしい驚きであり、こういう方法もあるんだという発見、自信にもなりました。もちろんいつもいつも『わからない』ばかりではダメですけど」。
回り道もあるからこそ、探究っておもしろい
※回り道もあるからこそ、探究っておもしろい!!
やはり挑戦して、失敗したとしてもあきらめないことが大切だと思っています。
仮定が崩されたとき、また仮定に立ち返る、時にはその仮定を疑ってみる、そして知識をおもちの専門家の方に聞いて、専門用語などの難しい言葉をかみ砕いて、おもしろくわかりやすく伝える。
大変な作業ですが、探究心こそが番組づくりの根幹であり、取材や編集の作業、過程の議論はとても楽しいですね」
喜怒哀楽など感情を意識することが、疑問をみつけるコツ!
※喜怒哀楽など感情を意識することが、疑問をみつけるコツ!
探究することのおもしろさや楽しさを感じている西ヶ谷さん。探究することを楽しむコツってあるのかな?
私は番組制作を通じて『なんでだろう?』という疑問をもつことが大切だと強く感じますが、その疑問が生まれるきっかけになるのが、喜怒哀楽などの感情だと思います。
例えば『おもしろい』と思ったとき、『なぜこれをおもしろいと思うのだろう?』と考えることで疑問が生まれ、育っていきます。
他にも『キレイだな』とか『楽しいな』とか、そういう感情が何かの興味を抱き、疑問をもつ入口になるんですね。
そして、疑問に対する答えはみんなが100%納得するものを目指したくなりますが、私はそうでなくていいと思っています。
『チコちゃんに叱られる!』という番組も、疑問の答えが出たから終わり、番組が完成したから終わりではありません。
調査の途中経過を見せたり、探し尽くしたはずだけどまだ探す余地があるかもと、番組が終わったあとも思考を続けることが大切なのではないかと感じています。
現に、サウスポーのネタはチームの中では『宿題』となっています」。
身近なものにこそ、探究のきっかけがあるとは意外!
「かわいい」「楽しい」「かなしい」「イライラする」など、普段の感情に着目すればいいなら、気軽に「探究」に取りかかれそうだし、純粋に「知りたい」「調べてみたい」という気持ちも生まれてくるはず。
貴重な高校時代、自分のものさしで探究することを楽しんで!
※日常に目を向けて探究学習を楽しんでみて♪
高校時代は、何にでも時間をかける権利があるのでは、という西ヶ谷さん。
「ボーっと生きてんじゃねえよ!」というチコちゃんの言葉のように、身の回りのことやモノに対する感情に少し疑問をもちながら毎日を過ごしてみるだけでも、調べたいことがどんどん浮かんでくるかも!
※2018年9月取材時点の内容です。
★ほかの記事もCHECK!
【対談】堀江貴文×高橋みなみが語る「価値あること」とは
それ本当にあってる?“知識を疑う”授業が公立高校でスタート!
「高校生の君たちへ」 キングコング西野亮廣が 今、思うこと
【対談】堀江貴文×チームラボ代表・猪子寿之が語る「アートが変える未来」