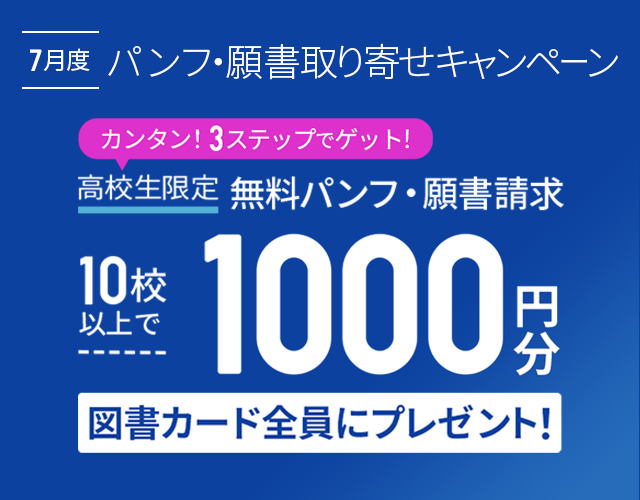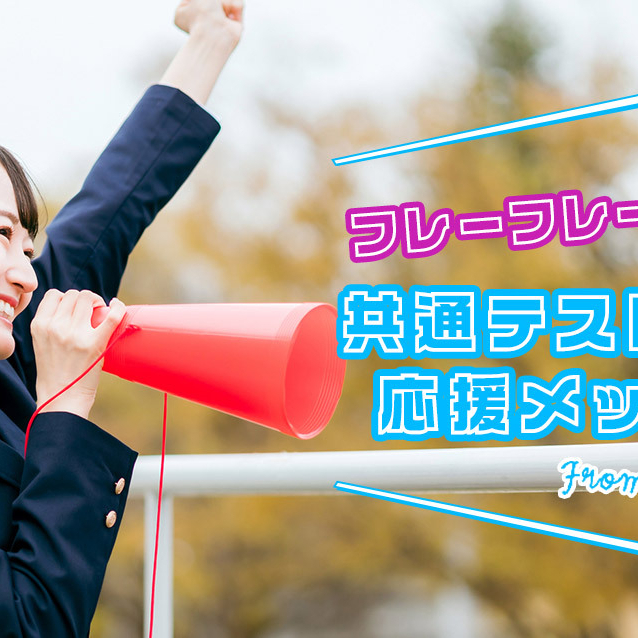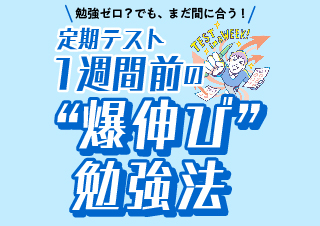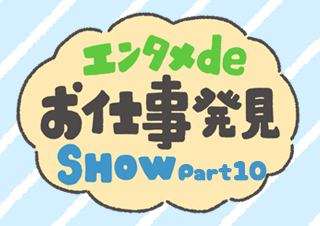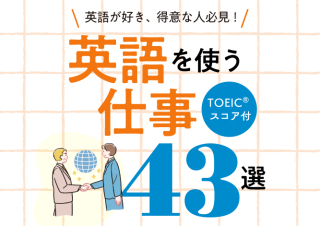「1人1台のタブレット端末」で授業がどんどんおもしろくなる?
最近、かなり身近に普及しているタブレット端末。iPad(R)などが有名だが、スマートフォンより大きめのA4サイズくらいの液晶画面で、タッチパネルで操作するのが一般的だ。
このタブレット端末を、政府が2020年までに、全国の小・中学校で“1人1台”整備する目標を掲げている。これに対してデジタル教科書協議会(以下DiTT)(※1)は、「2020年では遅すぎる、2015年までに実現しよう」と提案している。
事務局長で慶應義塾大学メディアデザイン研究科教授の中村伊知哉さんは、「すでに実現に向けた動きが各地で始まっています」という。
2014年4月からは佐賀県武雄市、東京都荒川区、2015年4月からは大阪府大阪市や大阪府箕野市、岡山県新見市など、いくつかの地方自治体で小・中学生全員にタブレット端末を持たせることが決まった。また佐賀県では2014年4月から県立高校の全1年生への配布を目指している。
一部ではあるが、すでに「1人1台のタブレット端末」を実現している学校もある。
千葉県立袖ヶ浦高校では2011年4月に情報コミュニケーション科を開設(各学年1クラス)。同科では全員がiPad(R)を購入し、すべての教科で活用している。
例えば、どういうふうに授業で活用されているかというと…
・漢文の授業で漢詩のイメージに合う写真を探す
・生物の授業で顕微鏡をのぞいて見える花粉を撮影する
・学校外に見学に出かける際にもっていって撮影したり、その場で気になることを検索するのに使う
・発表用の資料を作ったりするのに活用する
・SNS上で互いに意見を発表する
など、各教科で使い方は自由。聞くだけの授業とは違い、タブレット端末の新しい活用方法をどんどん発見しながら学べるため、生徒は主体的、積極的に授業に臨むことができているという。
お金をかけただけの効果が本当にあるのか? セキュリティの問題は? 視力が悪くならないか? ネット依存症は? …など、反対派の意見はいろいろある。
しかし中村さんによると、そのような問題はICT教育の先進国ではすでに解決済み。むしろ導入が遅れるほど、タブレット端末を使うことによって得られる新しい学びのチャンスが失われることが問題だという。
DiTTは2012年度、全国各地のいくつかの小・中学校で実証研究を行った(※2)。それによるとタブレット端末を使った授業は思いのほかうまくいき、子どもたちの反応はとてもよかったそうだ。
ある事例では、タブレット端末を使うメリットとして
・瞬時にみんなの意見をみんなで共有できる
・みんなで相互に意見が見られることで授業に集中する
・書くことで考えが整理される
・話すのが苦手な子でも、書くことによって平等に発言できる
・ワークシートの配布・回収の時間が不要になる
などがあげられた。
デジタル教科書をいちはやく導入した韓国では、デジタル教科書により、学力上位層よりも中間層から下位層の、大都市よりも小中規模都市の、さらに裕福な家庭よりも低所得層の家庭の生徒に、はっきりとした学力向上の効果がみられたそうだ。
この結果をみる限り、日本でも同じようにタブレット端末の力で教育格差を埋めることができるかもしれない。
1人1台のタブレット端末時代に向け、いよいよ動き出した日本。実現することで多くの子どもたちがメリットを享受できる体制が整うことを期待したい。
※1:DiTTのHPはこちら
※2:2012年度DiTT実証研究プロジェクトレポートより(レポート掲載URLはこちら PDFファイル)