模擬授業 美術館コレクション:いかにして作られたか・どう作っていくのか
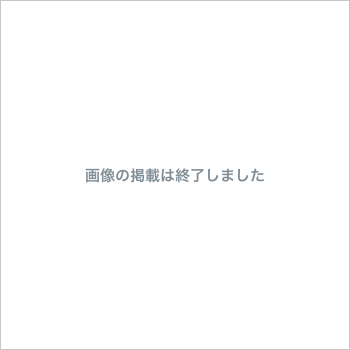
- 開催日時
-
-
2023年11月14日(火)18:30~20:00
-
11月21日(火)18:30~20:00
-
講座名
国立西洋美術館のコレクション:いかにして作られたか・どう作っていくのか
申込URL:
https://www.ou.tmu.ac.jp/web/course/detail/2331G112/
2021年春期より「日本の魅力ある博物館・美術館シリーズ」講座を実施しています。北海道から沖縄まで、日本全国の魅力ある個性的なミュージアムの学芸員や研究員が講師を担当し、コレクションや企画展について解説します。今期はル・コルビュジエ設計としても有名な国立西洋美術館です。常設展で見ることができる西洋絵画のコレクションや、その収集の歴史、さらに近年の新収蔵作品購入の様子まで、詳しくお話いただきます。
国立西洋美術館は西洋美術全般を対象とする唯一の国立美術館です。さらにはアジア最大の西洋美術コレクションを誇る美術館でもあります。
基礎にあるのは松方コレクションです。そしてそれは、ほとんど奇跡と言っていいような道のりを辿り、現在に伝えられました。
川崎造船所(現在の川崎重工業株式会社)の初代社長などを務めた松方幸次郎は、1916年以降約10年間のうちにヨーロッパで膨大な数の美術品を収集しました。その後、経済恐慌や第二次世界大戦といった苦難を経るあいだに、多くの作品は散逸し、あるいは火事で焼失してしまいます。そしてパリに残された最重要な部分(印象派の絵画およびロダンの彫刻を中心とするフランス美術コレクション)もまた、戦後フランス政府に接収される結果となりました。
日仏政府間の交渉を経て、1959年に作品群が寄贈返還されることになった折、それを展示公開する施設として設置されたのが、国立西洋美術館なのです。建物(現在の本館)を設計したのは近代建築の巨匠ル・コルビュジエでした。2016年7月に当館本館を含む世界7か国にまたがるル・コルビュジエの建築作品が世界遺産に登録されたことは、記憶に新しいことでしょう。
設立当初は370点の松方コレクションから出発した当館ですが、その後購入や寄贈によって作品を増やし、現在では主に中世から20世紀半ばまでに制作された、約6500点を収蔵しています。また、本館に加え1979年には新館が、1997年には企画館が竣工し、展示面積を大きく増やしました。企画館では年3回の特別展を開催しています。
●第1回:「松方コレクションと国立西洋美術館の成り立ち」
「日本の若い画家たちに本物の絵を見せてやりたい」―明治人らしい気概を持った松方幸次郎は、パリやロンドンの画商で作品を買いあさり、当地の話題をさらいました。印象派の大家モネからは直に購入しています。その後の恐慌による作品の散逸、戦時下の作品の疎開、戦後の政府間の返還交渉、建築家ル・コルビュジエとのやり取り…、さまざまなドラマを経て国立西洋美術館は開館します。第1回の講座では、松方コレクションの形成から国立西洋美術館の開館までを辿ります。
●第2回:「コレクションをつくり、調査する」
第2回の講座では、国立西洋美術館のコレクションが開館後いかにして増え、そして現在どのように拡大を続けているのかということを解説します。美術館が生きたものであるためには、作品の収集が欠かせません。当館もまた、開館後その収蔵品数を大きく増やし、現在も作品の購入や寄贈受け入れを継続しています。作品を収蔵する際は念入りな調査を行い、それは収蔵後も続けられます。関連する文献にあたることはもちろん、科学調査も取り入れて、真贋や来歴、美術史上の価値について判断します。講座では私自身が購入を担当した作品を取り上げつつ、コレクション形成の実際についても説明したいと思います。
講師:国立西洋美術館 学芸課長 渡辺 晋輔
国立西洋美術館のコレクション:いかにして作られたか・どう作っていくのか
申込URL:
https://www.ou.tmu.ac.jp/web/course/detail/2331G112/
2021年春期より「日本の魅力ある博物館・美術館シリーズ」講座を実施しています。北海道から沖縄まで、日本全国の魅力ある個性的なミュージアムの学芸員や研究員が講師を担当し、コレクションや企画展について解説します。今期はル・コルビュジエ設計としても有名な国立西洋美術館です。常設展で見ることができる西洋絵画のコレクションや、その収集の歴史、さらに近年の新収蔵作品購入の様子まで、詳しくお話いただきます。
国立西洋美術館は西洋美術全般を対象とする唯一の国立美術館です。さらにはアジア最大の西洋美術コレクションを誇る美術館でもあります。
基礎にあるのは松方コレクションです。そしてそれは、ほとんど奇跡と言っていいような道のりを辿り、現在に伝えられました。
川崎造船所(現在の川崎重工業株式会社)の初代社長などを務めた松方幸次郎は、1916年以降約10年間のうちにヨーロッパで膨大な数の美術品を収集しました。その後、経済恐慌や第二次世界大戦といった苦難を経るあいだに、多くの作品は散逸し、あるいは火事で焼失してしまいます。そしてパリに残された最重要な部分(印象派の絵画およびロダンの彫刻を中心とするフランス美術コレクション)もまた、戦後フランス政府に接収される結果となりました。
日仏政府間の交渉を経て、1959年に作品群が寄贈返還されることになった折、それを展示公開する施設として設置されたのが、国立西洋美術館なのです。建物(現在の本館)を設計したのは近代建築の巨匠ル・コルビュジエでした。2016年7月に当館本館を含む世界7か国にまたがるル・コルビュジエの建築作品が世界遺産に登録されたことは、記憶に新しいことでしょう。
設立当初は370点の松方コレクションから出発した当館ですが、その後購入や寄贈によって作品を増やし、現在では主に中世から20世紀半ばまでに制作された、約6500点を収蔵しています。また、本館に加え1979年には新館が、1997年には企画館が竣工し、展示面積を大きく増やしました。企画館では年3回の特別展を開催しています。
●第1回:「松方コレクションと国立西洋美術館の成り立ち」
「日本の若い画家たちに本物の絵を見せてやりたい」―明治人らしい気概を持った松方幸次郎は、パリやロンドンの画商で作品を買いあさり、当地の話題をさらいました。印象派の大家モネからは直に購入しています。その後の恐慌による作品の散逸、戦時下の作品の疎開、戦後の政府間の返還交渉、建築家ル・コルビュジエとのやり取り…、さまざまなドラマを経て国立西洋美術館は開館します。第1回の講座では、松方コレクションの形成から国立西洋美術館の開館までを辿ります。
●第2回:「コレクションをつくり、調査する」
第2回の講座では、国立西洋美術館のコレクションが開館後いかにして増え、そして現在どのように拡大を続けているのかということを解説します。美術館が生きたものであるためには、作品の収集が欠かせません。当館もまた、開館後その収蔵品数を大きく増やし、現在も作品の購入や寄贈受け入れを継続しています。作品を収蔵する際は念入りな調査を行い、それは収蔵後も続けられます。関連する文献にあたることはもちろん、科学調査も取り入れて、真贋や来歴、美術史上の価値について判断します。講座では私自身が購入を担当した作品を取り上げつつ、コレクション形成の実際についても説明したいと思います。
講師:国立西洋美術館 学芸課長 渡辺 晋輔
- 開催場所
-
飯田橋キャンパス東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館3階








