オンライン
開催イベント
量子物質理工学研究センター「量子物質が拓く新たな地平」
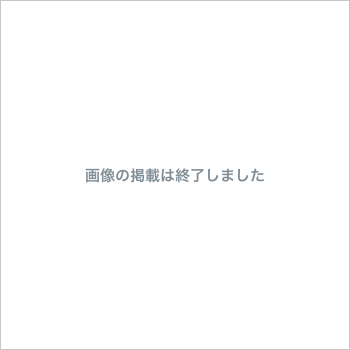
- 開催日時
-
-
2024年2月8日(木)18:30~20:00
-
2月15日(木)18:30~20:00
-
2月22日(木)18:30~20:00
-
2月29日(木)18:30~20:00
-
申込URL:https://www.ou.tmu.ac.jp/web/course/detail/2341G110/
※本講座はオンライン講座でライブ+見逃し配信で7日間何度でも視聴可。高校生のみ無料で1回だけの参加も可能です。
本研究センターは、2021年度末で終了した“超伝導理工学研究センター”を継続発展させた形で、2022年度より新たに発足したセンターです。ナノスケールの物質群に現れる量子電子構造、また超伝導や強相関現象などを広く量子現象として捉え、そのような量子現象が現れる物質群(量子物質)を軸に、理学・工学の学術領域の教員が横の連携を通して、新たな知と技術を創出することを目指す研究センターです。理学研究科物理学専攻や化学専攻において、新たな量子物質(ナノ構造物理、超伝導、強相関物質など)の物質創製を研究している教員や、電気・熱・分光測定手法を駆使して物性研究を行っている教員と、システムデザイン研究科機械システム工学域において表面・ナノ・マイクロデバイスを対象に研究を行っている教員が、分野横断的に連携することを目標としたセンターです。理学研究科において創出する新規ナノ構造・超伝導・強相関物質などに対して、工学の分野である微細加工技術・応用技術を融合することにより、新たなる量子現象や量子応用を実現することを目標とします。
センターの先進性:量子物質研究
ナノチューブ、ナノワイヤ、二次元物質といったナノスケールで特殊な構造をした物質、新たな積層・層状構造を有する物質、カイラル物質、トポロジカル物質、超伝導物質といった物質群においては、量子現象を起源とする新たな性質や機能が発現することが知られています。東京都立大学は、この分野の研究に強みがあり、本センターは、この量子物質を対象にした物質創製、物性探索、測定技術開発、デバイス応用、基礎理論、といった基礎から応用研究を行う教員が集い、研究交流と推進を担う研究拠点です。学科や研究室の枠にとらわれないセンターとして、分野横断した交流を通して、新たな知や技術を生み出していきます。またアウトリーチ活動や分野横断した教育活動も進めていきます。
本研究センターは、学科や研究室の枠に捉われない分野横断的な研究連携を通して、新たなる量子現象を見出すことや、量子応用を実現することを目標としています。
その最先端の研究成果を4回のシリーズで紹介します。
●第1回:ナノチューブ構造の材料をつかって温度差から電気エネルギーを取り出す
電気を流す物質は温度差があると電圧を発生します。これを熱起電力といいます。
私達の社会は様々な“熱”を再利用することなく捨てていますが、もしこの排熱を電気エネルギーに変換することができれば飛躍的な省エネルギーに繋がります。ナノスケールでチューブ構造を持つ材料の熱電変換の物性について解説します。
東京都立大学大学院 理学研究科 教授、研究センター長 柳和宏
●第2回:カイラル構造を持つ物質は何故面白い?
本講義では、「対称性」という観点で物質や物性をどうとらえるかという、物性物理学の基本的な考え方について話します。その上で、カイラル構造物質に関する話題を紹介します。
東京都立大学大学院 理学研究科 教授 松田達磨
●第3回:原子を積み重ねて結晶をつくる
私たちの身の回りの固体物質の多くは原子が規則正しく並んだ結晶で、その性質は固体中の原子の配列と密接に関わっています。本講義では、原子を一層ずつ積み重ねて結晶をつくる薄膜合成法と、人工的に制御された原子配列によって生まれる固体の性質について紹介します。
東京都立大学大学院 理学研究科 教授 廣瀬靖
●第4回:プリント技術を利用して薄膜やナノ材料を構造化する
厚さや直径が1μm(1/1000mm)以下の薄膜やナノ材料は、様々な機械的あるいは電気的な特性を持っています.それらをセンサなどのナノ・マイクロデバイスに応用するためには、狙ったとおりに形づくる(構造化する)技術が必要です。プリント(印刷)技術を利用した薄膜やナノ材料の構造化技術について解説します。
東京都立大学 システムデザイン学部 教授 金子新
※本講座はオンライン講座でライブ+見逃し配信で7日間何度でも視聴可。高校生のみ無料で1回だけの参加も可能です。
本研究センターは、2021年度末で終了した“超伝導理工学研究センター”を継続発展させた形で、2022年度より新たに発足したセンターです。ナノスケールの物質群に現れる量子電子構造、また超伝導や強相関現象などを広く量子現象として捉え、そのような量子現象が現れる物質群(量子物質)を軸に、理学・工学の学術領域の教員が横の連携を通して、新たな知と技術を創出することを目指す研究センターです。理学研究科物理学専攻や化学専攻において、新たな量子物質(ナノ構造物理、超伝導、強相関物質など)の物質創製を研究している教員や、電気・熱・分光測定手法を駆使して物性研究を行っている教員と、システムデザイン研究科機械システム工学域において表面・ナノ・マイクロデバイスを対象に研究を行っている教員が、分野横断的に連携することを目標としたセンターです。理学研究科において創出する新規ナノ構造・超伝導・強相関物質などに対して、工学の分野である微細加工技術・応用技術を融合することにより、新たなる量子現象や量子応用を実現することを目標とします。
センターの先進性:量子物質研究
ナノチューブ、ナノワイヤ、二次元物質といったナノスケールで特殊な構造をした物質、新たな積層・層状構造を有する物質、カイラル物質、トポロジカル物質、超伝導物質といった物質群においては、量子現象を起源とする新たな性質や機能が発現することが知られています。東京都立大学は、この分野の研究に強みがあり、本センターは、この量子物質を対象にした物質創製、物性探索、測定技術開発、デバイス応用、基礎理論、といった基礎から応用研究を行う教員が集い、研究交流と推進を担う研究拠点です。学科や研究室の枠にとらわれないセンターとして、分野横断した交流を通して、新たな知や技術を生み出していきます。またアウトリーチ活動や分野横断した教育活動も進めていきます。
本研究センターは、学科や研究室の枠に捉われない分野横断的な研究連携を通して、新たなる量子現象を見出すことや、量子応用を実現することを目標としています。
その最先端の研究成果を4回のシリーズで紹介します。
●第1回:ナノチューブ構造の材料をつかって温度差から電気エネルギーを取り出す
電気を流す物質は温度差があると電圧を発生します。これを熱起電力といいます。
私達の社会は様々な“熱”を再利用することなく捨てていますが、もしこの排熱を電気エネルギーに変換することができれば飛躍的な省エネルギーに繋がります。ナノスケールでチューブ構造を持つ材料の熱電変換の物性について解説します。
東京都立大学大学院 理学研究科 教授、研究センター長 柳和宏
●第2回:カイラル構造を持つ物質は何故面白い?
本講義では、「対称性」という観点で物質や物性をどうとらえるかという、物性物理学の基本的な考え方について話します。その上で、カイラル構造物質に関する話題を紹介します。
東京都立大学大学院 理学研究科 教授 松田達磨
●第3回:原子を積み重ねて結晶をつくる
私たちの身の回りの固体物質の多くは原子が規則正しく並んだ結晶で、その性質は固体中の原子の配列と密接に関わっています。本講義では、原子を一層ずつ積み重ねて結晶をつくる薄膜合成法と、人工的に制御された原子配列によって生まれる固体の性質について紹介します。
東京都立大学大学院 理学研究科 教授 廣瀬靖
●第4回:プリント技術を利用して薄膜やナノ材料を構造化する
厚さや直径が1μm(1/1000mm)以下の薄膜やナノ材料は、様々な機械的あるいは電気的な特性を持っています.それらをセンサなどのナノ・マイクロデバイスに応用するためには、狙ったとおりに形づくる(構造化する)技術が必要です。プリント(印刷)技術を利用した薄膜やナノ材料の構造化技術について解説します。
東京都立大学 システムデザイン学部 教授 金子新








