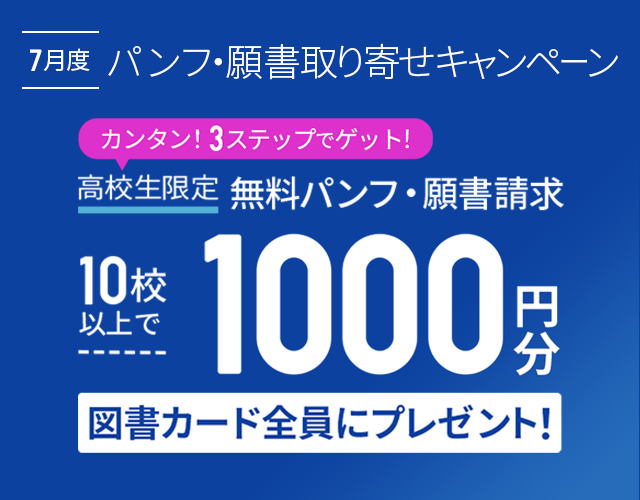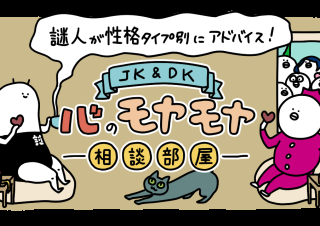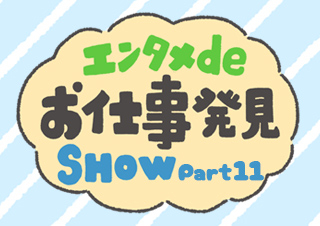アニメにかかわる仕事って、どんな種類があるの? アニメーター、声優、脚本家まで解説!
アニメが好き、アニメを作ってみたい、アニメ業界に興味があるという高校生のなかには、アニメにかかわる仕事にあこがれている人も多いはず。そこで、アニメにかかわる仕事にはどんな種類があるのか、仕事内容、アニメにかかわる仕事に就くにはどうすればいいのかを紹介しよう。
さらに、実際に3DCGアニメを制作しているCGアニメーターに、仕事内容や働き方、やりがいについても聞いてみた。
目次
アニメにかかわる仕事とは?
アニメにかかわる仕事は大きく分けて3つ
アニメにかかわる仕事は、大きく分けると「プリプロダクション」「プロダクション」「ポストプロダクション」の3つ。「プリプロダクション」が企画を立てて、シナリオやキャラクターデザインなどを制作。
「プロダクション」でアニメーターが作画や彩色をしたアニメーションに、「ポストプロダクション」が声優のボイスや効果音などを収録、編集をして、1本のアニメ作品を完成させる。

アニメ作品の大枠を作って指揮する仕事(プリプロダクション)

「プリプロダクション」の仕事は、アニメ作品の企画を立てるところから始まり、ストーリーやキャラクターを決めて、絵コンテを制作するまでの工程を担当。
視聴者を引き込むしかけづくりをして、アニメ制作の指揮をとる、まさにアニメ作品の土台となる大切な仕事なのだ。
プリプロダクションの主な仕事内容としては、
①企画
②プロット
③シナリオ
④設定・デザイン
⑤絵コンテ
これらの仕事を行っている職種は、
1.プロデューサー
2.監督・ディレクター
3.脚本家・シナリオライター
4.デザイナー・クリエイター・アニメーター
5.演出家
など。
例えば、監督がシナリオや絵コンテまで描いて複数の仕事を兼務することがある一方で、デザインはキャラクター・メカ・美術といった専門のデザイナーが担当するなど分業で行っている仕事もある。
1.プロデューサー
アニメ作品の企画立案をしたり、制作資金を調達したりする、ビジネスサイドの「企画プロデューサー」と、アニメ制作のスケジュールを管理したり、制作現場の指揮をする、現場サイドの「制作プロデューサー」がいる。アニメ制作の最初の仕事になる「企画」は、企画プロデューサー主導で行われるのが一般的。
制作プロデューサーは、プロダクションでのアニメーターの仕事の制作管理がメインの仕事になる。
2.監督・ディレクター
アニメ作品の総責任者となるのが、映画監督やテレビディレクター。どんなアニメ作品を制作したいか、企画の段階から関わり、プロットやテレビアニメのシリーズ構成をシナリオライターと一緒に考えたり、シナリオや絵コンテまで手がけたりする監督もいる。
3.脚本家・シナリオライター
文字ベースで、作品のストーリーやセリフなどを考えて、アニメ作品の脚本やシナリオを書く仕事。企画プロデューサーや監督・ディレクターなどと打ち合せをしながら、監督と一緒に脚本やシナリオを書いたり、複数の脚本家・シナリオライターで分業したりして書くこともある。
4.デザイナー・クリエイター・アニメーター
キャラクターデザイン、メカデザイン、美術(背景)デザインなど、それぞれ担当のデザイナーやクリエイターがアニメ作品の指針となるデザインを設定している。アニメーターが作画するときのベースになるため、誰が描いても違和感がないよう、例えばキャラクターデザイナーはキャラクターの正面・横・後ろ姿などを線画で細かく描き、美術デザイナーは背景の世界観まで設定。
美術デザインは、美術監督が背景や小物などキャラクター以外のデザインを決めることが多いようだ。
5.演出家
脚本やシナリオに書かれた文字ベースのストーリーを絵に描き起こしたものが絵コンテ。アニメーターは絵コンテを基に作画していくため、アニメ作品の重要な設計図といえる。
1話30分のテレビアニメの場合、300カット程度の絵コンテが必要になるが、そのカットごとの構成を考えて絵コンテを描くのは、演出家の仕事のひとつ。
監督が絵コンテまで描くことがあるほか、監督や演出家が考えたイメージをコンテマンという絵コンテ専門のスタッフに伝えて、コンテマンが制作する場合もある。
完成した絵コンテからアニメーターがレイアウト作業したものまで、すべての構図や芝居の確認作業、修正作業を行うのも演出家の役目なのだ。
アニメ制作のメインとなる絵を描いて動かす仕事(プロダクション)

「プロダクション」の仕事は、作画をして、色を着け、キャラクターなどと背景を合成して、音のないアニメーションを作るまでの工程を担当。
キャラクターにイキイキとした動きをつけて、魅力的なアニメ作品の世界を作り上げる、アニメ制作のメインとなる仕事なのだ。
アニメ映画のエンドロールで、声優の名前だけでなく、「原画」「動画」「背景」など、たくさんのアニメーターの名前が流れるのを見たことがある人は多いだろう。
プロダクションでのアニメ制作の仕事はとても細かい分業になり、1本のアニメ作品を作るためには数百人ものアニメーターが関わっている。
長編アニメ映画の場合、ちょっとしたお手伝い程度の人も含めると1000人近いアニメーターがアニメ制作にかかわることもあるとか。
アニメ制作の手法とそれらを行う職種は、
6.アナログ手法(手描き)のアニメーター
7.デジタル手法のアニメーター
8.3DCGのアニメーター
の3種類。
絵を描く方法が異なるが、いずれも細かく分業されていて、さまざまな専門スキルをもったアニメーターが担当している。
6.アナログ手法のアニメーター
アナログ手法(手描き)のアニメーターの仕事は、●レイアウト
●原画
●動画
●背景美術
●色彩
●ペイント
●撮影
に分かれている。
プロダクションでの主な工程としては、
①レイアウト担当のアニメーターが、絵コンテを基にカットごとの構図やキャラクターの配置、どういうアングルで見せるかを決める。
②作画(キャラクター)担当と美術(背景)担当に分かれて、それぞれ手描きで原画を描く。
③作画担当のアニメーターは、さらに原画マンと動画マンに分かれていて、原画マンはキャラクターのキーとなるポーズだけを描き、その間をつなげるカットを動画マンが描く。
例えば動きのあるシーンなら、動く前と動いた後の2カットを原画マンが描き、動いている途中の複数のカットを動画マンが描いて、キャラクターに動きをつけるのだ。
④背景美術担当の美術クリエイターは、背景画だけを描き、キャラクターは描かない。
レイアウト・原画・動画は、紙に鉛筆や色鉛筆で描いているが、アナログ手法といっても手描きで制作するのは、この工程まで。
⑤原画・動画・背景美術のアニメーターや美術クリエイターが描いた絵をパソコンでスキャンして、ペイント担当のアニメーターが彩色をする。
1990年代まではセル画という透明シートに絵をトレースして手描きで色を塗っていたが、最近は彩色の工程以降がデジタル化され、ペイントはパソコンでの作業になっている。
⑥キャラクターの色を決める色彩設計、どこを何色で塗るのかをカットごとに細かく指示する色指定のアニメーターがいて、ペイント担当のアニメーターは、その指示に従って彩色をする。
⑦撮影担当のコンポジットクリエイターが、仕上がったキャラクターと背景などの素材を合成して画面処理を行う。
セル画をカメラで撮影していたなごりで「撮影」と言っているが、実際にはパソコン上での作業になり、撮影監督の指示のもと、コンポジットクリエイターがカットごとの動画を仕上げている。
例えばテレビアニメの場合、1話300カットの作品には5000枚程度の絵が必要になるため、たくさんのアニメーターがカットごとに担当分けして、1本の作品を作っているのだ。
7.デジタル手法のアニメーター
 |
 |
デジタル手法のアニメーターの仕事は、アナログ手法(手描き)のアニメーターとほぼ同じ工程。
最初のレイアウトから作画や背景美術など、全工程をパソコンで行い、手描きで作業することはない。
8.CGアニメーター

CGアニメーターの仕事は、デジタル手法のアニメーターと作業自体は変わらないが、3Dソフトを使用して、平面ではなく立体的に見せるための工程が加わる。
CGアニメーターの制作工程は、キャラクターやオブジェクトの素材を作る「アセット」と、素材をレイアウトして動きなどをつける「カット制作」の2つに分けられる。
●アセット
①モデリングを担当するモデラーが、キャラクターをはじめ、大道具・小道具、建物、乗り物などのオブジェクトのモデルを作る。
②リギングを担当するリガーが、キャラクターやメカなどを動かすためのしくみ「リグ」を仕込む。
例えば、キャラクターに関節をつけて肘や膝がスムーズに曲がるようにするのはリガーの仕事。
③質感設定担当が、キャラクターやオブジェクトにリアルな質感がでるよう設定する。
●カット制作
①3Dレイアウト担当が、3D空間の中にキャラクターやオブジェクトを配置して、画面の構図やカメラワークを決める。
②モーション担当が、キャラクターなどにスムーズな動きをつけたり、表情に変化をつけたりしている。
③ライティング担当が、どこに光をもっていくか設定して、立体的に見えるようなライティングや明暗などを考える。
④3Dエフェクト担当が、土煙や爆発、炎など、効果的な演出を加える。
●仕上げ
①レンダリング担当が、データを書き出して、画像化する。
②撮影担当のコンポジットクリエイターが、3Dで制作されたものにフィルターをかけたり、背景とキャラクターをなじませたり、調整を行う。
アニメ動画に音声を収録して編集する仕事(ポストプロダクション)

「ポストプロダクション」の仕事は、プロダクションで制作した動画に音声を収録し、1本のアニメ作品として仕上げる最終工程になる。
ポストプロダクションの主な仕事内容としては、
①CT(カッティング)編集
②アフレコ
③音響
④ダビング
⑤V(ビデオ)編集
これらの仕事を行っている職種は、
9.編集クリエイター
10.声優
11.音響監督
12.音響エンジニア・サウンドクリエイター
など。
9.編集クリエイター
プロダクションで制作されたカットごとにバラバラになっている動画をつなげ、カットとカットの間を微調整して、決められた尺に合うよう、CT(カッティング)編集をする。プロデューサー、監督・ディレクター、演出家などが立ち会って、最終的にカットのつながりを調整して、1本のアニメ作品を完成させるV(ビデオ)編集も担当している。
10.声優
各キャラクターを担当する声優が、アフレコで、キャラクターの話し方や動きに合わせてセリフを読み上げ、感情豊かに表現する。11.音響監督
音の演出の総責任者として、声優のアフレコに立ち会って演技指導をしたり、どのシーンにどんなBGMを流すのか、どんな効果音を入れるのかを決めたりする。監督やディレクターと一緒に音響を考えることもある。
12.音響エンジニア・サウンドクリエイター
音響監督の指示に従って、BGMを選んだり、効果音を制作して、声優のボイスも一緒に映像に収録するダビングという工程を担当している。

アニメにかかわる仕事に就くには?

大学や専門学校で専門知識を身につける
アニメにかかわる仕事に就くために必須の資格はなく、学歴も問われないことが多いが、アニメーターになるには、うまく絵を描いたり、表現したりする画力が求められる。さらに、アニメ制作に使用するソフトは高額のものもあり、独学でソフトを操作するスキルを身につけるのは難しいこともあり、大学や専門学校の美術・デザイン系またはアニメーション専門コースで、アニメ制作の基礎を学び、画力を磨いてから就職する道が一般的。
高校卒業後に未経験でアニメ制作会社やスタジオに就職することは可能だが、大学や専門学校で、アニメ制作に必要な専門知識やスキルを身につけてから仕事に就くのが望ましい。
アニメ制作会社やスタジオに就職する
アニメにかかわる仕事に就くには、大学や専門学校を卒業後、アニメ制作会社やスタジオなどに就職する人が多い。アニメ制作会社には、映画会社やテレビ局と直につながっている元請けの大手アニメ制作会社から、制作業務を請け負う下請けの中小のプロダクション、さらに一部の下請けを担う原画・動画・背景などに特化した専門スタジオまであり、大小さまざまな規模の会社が協力しあって、1本のアニメ作品を作り上げている。
「プリプロダクション」の仕事をするには、企画や制作管理を行っている元請けの制作会社への就職を目指そう。
経験を積んだらフリーランスで活躍する道も
アニメにかかわる仕事では、プロデューサー、監督・ディレクター、脚本家・シナリオライター、デザイナー・クリエイター、演出家、アニメーター、声優など、さまざまな職種でフリーランスとして活躍することが可能。アニメ業界は横のつながりが広い特殊な業界で、複数の制作会社が共同で1本のアニメ作品を作り上げることもあるため、ライバル視するという意識が少ないといわれている。
そのため、実力さえあれば、同じようなジャンルの作品を制作している複数の会社の仕事を同時に請け負うこともできるのだ。
まずは制作会社やプロダクション、専門スタジオなどで実績を上げることで、フリーランスとしての道が開けてくる。
就職して1年程度で独立する人もいれば、10年以上じっくりと経験を積んでからフリーランスになる人もいて、個人差は大きい。
ただし、3DCG制作は高額なソフトを使用するため、個人で設備をそろえるのが難しく、フリーランスで働くCGアニメーターは少ない現状があるようだ。
アニメーターは動画マンからスタート
アニメ制作で最も多くのスタッフが関わっている作画担当のアニメーターになる場合、まずは動画マンからスタート。原画マンが描いたキャラクターのポーズをつなげる間のカットを描くことで画力を磨いていき、スキルアップすると原画をまかされるようになっていく。
さらにステップアップすると、多くの原画マンが描いたキャラクターの表情などを統一させる作画監督、キャラクターデザイナーをめざすこともできる。
アニメ制作に求められるスキルは?

柔軟な思考をもっている人が向いている
アニメーターの場合、必ずしも自分が描きたい絵を描けるわけではない。仕事である以上、描きたくないキャラクターや苦手な絵を描かなければいけないときもあるだろう。
それに対応できる柔軟な思考をもっている人がアニメーターに向いている。
まじめすぎたり、こだわりが強すぎたりすると、制作に時間がかかってしまい、多くの仕事をこなすことができない。
納期が近いと残業が多くなるケースもあるので、体力がある人のほうが安心。
ただ最近は労務管理をしっかりしてくれる会社が増えてきているので、昔ほどブラックな業界ではなくなっているようだ。
人や物の動きや構造を見る観察力が必要
たくさんのアニメ作品を観ることは大事だが、自分のまわりにあるものや実体験も、アニメ制作に役立つ。例えば、植物がどういうふうに生えているのか、建物はどんな構造になっているのか、目に入るものをしっかりと観察する力が求められる。
こういうときにはこんな表情をするのだな、疲れている人と元気な人では歩き方がこんなに違うんだな、というように注意して人を観察すると、日常生活にたくさんのヒントがあるはず。
普段、何気なく見ているものをじっくり観察して、そのしくみや動きについて考えてみるようにすると、アニメーターの仕事に生かすことができるのだ。
絵を上手に描くスキルはあったほうがよい
アニメーターになるには、絵を上手に描くスキルがあるほうが望ましい。とはいえ、アニメーターの仕事は原画マンが描いたキャラクターをマネして描くことからスタートするため、練習することで絵のスキルはアップしていく。
また、アニメにかかわる仕事には、さまざまな役割があるため、必ずしも絵を上手に描くスキルが求められるわけではない。
人物を描くのは苦手だけど風景や物の絵を描くのが好きな人は、背景美術を専門にすればいいだろう。
また、絵のセンスがなくても、こういうものを作りたいと求められている完成形がイメージできる人は、CGアニメーターが向いている。
3DCGの場合、ツールの使い方さえマスターして、ソフトを使いこなすことができれば、手描きで絵を描くのが得意でなくても、CGアニメーターとして仕事をすることが可能。
また、プロダクションなどに勤務する制作管理担当の仕事は、クリエイティブな仕事に携わらないことが多い。
制作管理担当は、たくさんの工程を把握して、アニメーターやクリエイターに仕事を割りふって納期を管理するのが仕事なので、クリエイティブなスキルよりも管理能力が求められている。
アニメにかかわる仕事の将来性は?
アニメ業界は人材不足。能力さえあれば稼げる
アニメ制作には多くの工程があり、さまざまな役割があるので、自分に合った仕事が見つかるかもしれない。テレビや映画など、数えきれないほどのアニメ作品が次から次へと制作されていて、アニメ業界は人材不足なので、スキルがあればフリーランスでも重宝されるはず。
原画の制作費は1カット5000円程度だが、内容やアニメーターの能力によって1時間で描ける場合もあれば、数時間かけても終わらないことも。
実力至上主義の世界なので、フリーランスの場合は能力さえあれば、やった分だけ、いくらでも稼ぐことが可能。
かわいい女の子を描くのが上手な人もいれば、カッコイイ男の子しか描けない人もいるだろう。
実績を上げることで、得意なキャラクターや絵だけを担当することもできるようになる。
さらにステップアップして、キャラクターデザイナーや総作画監督、ディレクション的な立場になると、月に100万円以上、稼ぐ人もいるとか。
アニメ作品では、エンドロールにスタッフ全員の名前を流してもらえることが多いため、励みになるし、フリーランスの営業ツールとして活用することもできるのがメリット。
CGアニメーターにインタビュー!

株式会社ギークトイズに勤務して、さまざまなアニメ作品を3DCGで制作している、CGアニメーターの大澤裕章さんに話を聞いてきた。
CGアニメーターになろうと思ったきっかけは?
もともとゲームが好きで、アニメも観ていたので、仕事にするなら好きなことのほうがおもしろいかな、という軽い気持ちでした。
専門学校入学時はCGの知識もスキルもゼロの状態で、パソコンにも詳しくなかったから、覚えなくてはいけないことが多くて大変。
家で夜遅くまで勉強することもあったけれど、自分のイメージしたものが実際に3DCGの形となっていくのがおもしろくて楽しかったから続けられたと思います。
パソコン初心者でも勉強についていけないということはなかったですね」
(大澤さん)
CGアニメーターの仕事内容は?
絵コンテを基に、レイアウトしてキャラクターを配置し、キャラクターに動きをつける重要な仕事です。
キャラクターの設定や動きの方向性、キャラクターがもっている性格まで読み込んで理解し、イメージしながら動きをつけていきます。
シーンやカットごとに担当が分けられていて、ほかのCGアニメーターが制作したカットとつなげるため、スムーズな流れになるよう心がけています。
基本は、ひとりでパソコンに向かって黙々と作業していますが、チームのメンバーと、こういう動きはどうしたらいいか、などと話し合うことも。
自分がいいなと思っていることが必ずしも正解ではなく、監督の意向をくみ取って反映させていかなければならないので、そこが難しいところですね。
キャラクターが1人で静止しているシーンなら1カット1時間程度で制作することもできますが、複数のキャラクターが複雑に動いているシーンになると丸1日かけても終わらないケースもあります」
(大澤さん)
CGアニメーターの仕事のやりがいは?
ある意味、楽しさと苦しさが表裏一体ですが、イメージしたとおりの動きが再現できたときは、とてもやりがいを感じますね。
たとえスケジュールが短くても、クオリティーを落とさないよう、こだわって仕事をしています。
すごく良いシーンを寝る間も惜しんで取り組み、いいものができたときは、大きな達成感があって楽しかったです。
自分が手がけたアニメ作品をたくさんの人に観てもらうことができて、エンドロールで自分の名前が流れる、仕事の成果が目に見えるのが一番のやりがい。
友人に自分の仕事の話をすると盛り上がるし、ほめられるとうれしくなります。
メインキャラクターや難しいカットをどんどんまかされるようになり、じっくりとクオリティーを上げていくのが目標。
カッコイイ系の派手な動きのあるシーンを制作していきたいですね」
(大澤さん)
CGアニメーターになるにはどうすればいい?
最初は簡単なカットから始めて、経験値を上げることで難しいシーンへとスキルアップしていけばいいのです。
アニメーターの仕事は観察力が大事。
アニメ作品を観ていて、『カッコイイ!』『かわいい♡』と心を動かされるシーンがあったら、なぜそう思ったのかを考えてみましょう。
例えば、表情がいいとかポーズがいいとか、動きと動きの間の細かいところにも目を配って言語化していくこと。
自分の頭の中で整理していくと、いろいろな気づきがあり、それを自分の中に落とし込んでいくことで、実際に仕事をするときの参考になると思います。
有名なシーンには、人の心を動かす理由があるはずなんです。
ただ感動するだけでなく、レイアウトやポージングなどを分析して、それをマネしてみると勉強になりますよ。
ぼく自身も、好きなジャンルだけでなく、いろいろな作品を観るようにしています。
1カット1カットのつながりを見るために、コマ送りにして分析することも。
アニメ作品だけでなく、実写映画も参考にしながら、観察力を養っていくといいですね」
(大澤さん)
CGアニメーターをめざす高校生へのメッセージ
興味があるのにやらないと、後悔すると思います。
ぼくは後悔したくなかったから、3DCGの専門学校に進みました。
実際にやってみないと、自分に合うか合わないかはわかりません。
中には、アニメを観るのは大好きだけど、アニメーターの仕事は自分には向いていなかった、と気づく人もいるでしょう。
でも、アニメーター以外にもアニメにかかわる仕事はいろいろあるので、アニメが好きなら、一度は挑戦してみてほしいですね」
(大澤さん)
アニメにかかわる仕事には、絵を描くアニメーターをはじめ、さまざまな仕事がある。
1本のアニメ作品には、数多くのスタッフが携わっていて、アニメーターの仕事だけでも細かく分業されているから、絵が上手に描けない人に向いている仕事も見つかるはず。
アニメが好きな人は、アニメ業界の中で自分にピッタリの仕事を探してみよう。



取材協力/株式会社ギークトイズ
取材・文/やまだみちこ 撮影/沼尻淳子 構成/高木龍一(本誌)
※この記事は2023年2月に取材したものです。
★関連記事をチェック
イラストレーターの仕事ってどんな仕事?人気イラストレーターせきやゆりえさんに聞く
『ちはやふる』の作者・末次由紀先生に聞く 高校生でマンガ家デビューする方法