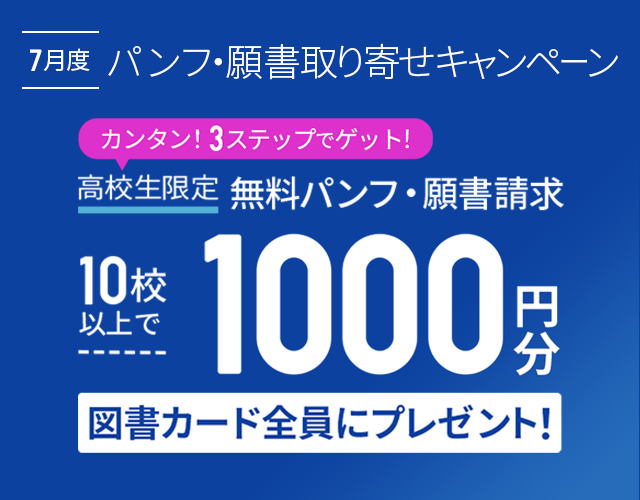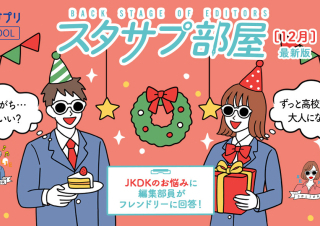不登校だったぼくが、不登校専門紙の編集長になるまで
不登校・引きこもりの本人とその家族を対象とした、タブロイド版「Fonte(フォンテ)」とウェブ版「不登校新聞」。その編集長を務めるのは、自ら不登校経験を持つ石井志昂(しこう)さん(31歳)だ。
一度は死まで考えた石井さんが、どのように編集長になるに至ったのか――これまでの半生を振り返ってもらった。
■中2で不登校。生きる自信を失った
不登校の前兆は、すでに小学校5年生ころにあったという石井さん。中学受験のためにスパルタ塾に入り、強いストレスを感じる生活を送っていた。情緒不安定になり、ゴミ箱や小さな物を燃やす火遊びを繰り返すなど、問題行動が出たほどだった。
そんな苦労の末に臨んだ中学受験だったが、すべて不合格。公立中学へ進学することとなった。両親の落胆はひどく、石井さんは罪悪感と劣等感に苦しむことに。また、小学校とは違う服装規定や先輩との上下関係などの中学特有のルールに不条理を感じ、学校に行くことが苦しかったという。
「最も落胆したのは、目の前にいる先生たちが誰も楽しそうではなかったこと。『自分もこういうふうにつまらない人生を歩むんだ。なぜなら自分は中学受験を失敗したから。負け組になってしまったから』…という思いがどんどん高まっていきました」(石井さん、以下同)
そして、学校へは中2で行かなくなった。しかし、学校に行かないと、ラクになるどころか、罪悪感や劣等感がさらに膨れ上がっていった。「生きてちゃいけないんじゃないか」と、命を絶つことを決めた日もあったという。
「生きていく自信を丸ごとなくした」と石井さん。しかし、それが石井さんにとってはスタートだった。
■不登校でメシを食べていく
16歳の時、不登校新聞社との出会いが転機となった。不登校新聞社には「子ども若者編集部」があり、不登校や引きこもりの当事者が記者として取材や制作にかかわっている。「おもしろそうだな」と興味をもった石井さんは、その一員としてかかわるように。著名人インタビューに自分でアポイントメントを入れて写真撮影までこなしたり、正規スタッフと一緒に韓国まで取材に行ったり…。そんな活動に、石井さんは楽しさを見いだした。
「学校のテストでは“答え”を探すのに必死でしたが、社会で大事なのは“問い”のほう。さまざまな方に取材するなかで、そう感じました。そして、不登校新聞では自分の問いが大事にされることが、とても新鮮でした。例えば、自分が不登校だった時に『自分は生きていてはいけないんじゃないか』と思っていたのですが、それが『じゃあどんな人間だったら生きていていいのか?』という問いが取材テーマとして生きてくるんです」
19歳の時、同社代表に直談判し正規スタッフになり、24歳で編集長に就任。自身の経験をふまえ、不登校・引きこもり当事者の目線のメディア作りをしてきた。
「これからも“不登校”でメシを食べて、長生きすることが目標」と石井さん。そう考えるようになったのは、10代のころに取材した在日韓国人の実業家、辛淑玉(しんすご)さんの話がきっかけになっている。
「辛さん自身も“在日コリアン”であることを売ってここまできたというお話で、『あなたは“不登校”を売ったらいい』と言われたんです。それを聞いて、最初はすごく腹が立ちました。私の不登校は商品じゃないぞと。でも、後々、ああそうか、不登校は自分にとって大きな武器だな、と思うようになったんです」

(上写真:子ども若者編集部スタッフと石井編集長)
■自分自身を否定しないでほしい
不登校新聞編集長として目指していることは、「不登校・引きこもりを全面肯定すること」だという。
「不登校や引きこもりをしたからといって、責められたり、命を落としたりする必要はありません。だから、自分自身を否定しないでほしい。そして、どうにか現状を突破してほしい。不登校新聞がその力になれたらうれしいですね」
どん底の気分を味わっても、その経験を武器に立ち上がった石井さん。その半生から学べることは多そうだ。
<参考>
NPO全国不登校新聞社発行
・タブロイド版「Fonte(フォンテ)」(月2回発行・月額800円)
・ウェブ版「不登校新聞」(月2回発行・月額800円)
※トップ画像 撮影:高松英明