オンライン
開催イベント
武田信玄の治水施設群を分析する -洪水氾濫シミュレーション-
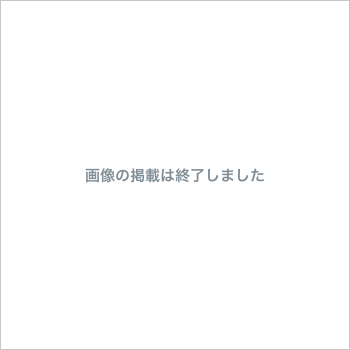
- 開催日時
-
-
2023年11月25日(土)10:00~11:30
-
講座名
治水の祖 武田信玄の治水施設群を分析する
-洪水氾濫シミュレーションを用いて-
申込URL
https://www.ou.tmu.ac.jp/web/course/detail/2331Z005/
一般的に「信玄堤」と呼ばれる堤防は、御勅使川と合流した直後の釜無川の左岸側に築かれた現在の信玄堤公園にある堤防のことですが、これは「狭義の信玄堤」です。「広義の信玄堤」とは、御勅使川の上流から築かれた石積出、白根将棋頭、竜岡将棋頭、堀切、十六石、龍王川除(狭義の信玄堤)、霞堤の一連の治水施設群のことを指します。これらの一連の治水施設群は、単に洪水が起こった際に洪水流が堤防を越えないようにするための治水施設ではなく、御勅使川の流路を根本的に変えることによって、洪水が起こったとしても甲府の町が守れるようにした大規模な治水コントロールシステムです。信玄堤は以下のようなことを行っていたと言われています。
1.石積出で御勅使川の流路を北東へ誘導します。
2.白根に将棋の駒型の堤防である将棋頭を築き、御勅使川の流れを北流と南流の2つに分け、水の勢いを2つに分けます。
3.竜岡にも将棋頭にて、御勅使川の北流をさらに2つに分けます。
4.十六石と呼ばれる16個の巨石によって、御勅使川とスムーズに合流させられるように、釜無川の流れを整えます。
5.竜岡台地に堀切を掘ることによって、御勅使川の北流を北東に向け、南東へ流れようとする釜無川と合流させて、南北の勢いを相殺させ、東の高岩へと流れを向けます。
6.天然の岸壁である高岩に釜無川をぶつけて、流れを跳ね返らせて、南に転じさせます。
7.御勅使川南流を合流させ、高岩から跳ね返ってきた釜無川の流れを整えます。
8.龍王川除や霞堤を築いて、洪水が起こった場合でも、遊水池に逃がせるようにします。
このような大規模な治水コントロールシステムですが、現在、信玄堤の御勅使川沿いの治水施設は、明治時代以降の治水事業によって、その機能は果たしていません。しかし、飛行機も土木機械もなかった戦国時代において、川の流路を変えてまで甲府の町を守ったその技術や考え方は、現在の防災においても役立つことがあるかもしれません。
洪水氾濫シミュレーションは、地形や流量などの設定を変えて、何度も実験をすることができるコンピュータシミュレーションです。近年では、ハザードマップの作成などにも活用されています。本講義では、洪水氾濫シミュレーションの結果を見ながら、信玄堤の各治水施設群の治水能力を確認しつつ、信玄の行った治水事業と現在の防災について考えてみましょう。
講師:東京都立大学 学術情報基盤センター 特任准教授 根元 裕樹
治水の祖 武田信玄の治水施設群を分析する
-洪水氾濫シミュレーションを用いて-
申込URL
https://www.ou.tmu.ac.jp/web/course/detail/2331Z005/
一般的に「信玄堤」と呼ばれる堤防は、御勅使川と合流した直後の釜無川の左岸側に築かれた現在の信玄堤公園にある堤防のことですが、これは「狭義の信玄堤」です。「広義の信玄堤」とは、御勅使川の上流から築かれた石積出、白根将棋頭、竜岡将棋頭、堀切、十六石、龍王川除(狭義の信玄堤)、霞堤の一連の治水施設群のことを指します。これらの一連の治水施設群は、単に洪水が起こった際に洪水流が堤防を越えないようにするための治水施設ではなく、御勅使川の流路を根本的に変えることによって、洪水が起こったとしても甲府の町が守れるようにした大規模な治水コントロールシステムです。信玄堤は以下のようなことを行っていたと言われています。
1.石積出で御勅使川の流路を北東へ誘導します。
2.白根に将棋の駒型の堤防である将棋頭を築き、御勅使川の流れを北流と南流の2つに分け、水の勢いを2つに分けます。
3.竜岡にも将棋頭にて、御勅使川の北流をさらに2つに分けます。
4.十六石と呼ばれる16個の巨石によって、御勅使川とスムーズに合流させられるように、釜無川の流れを整えます。
5.竜岡台地に堀切を掘ることによって、御勅使川の北流を北東に向け、南東へ流れようとする釜無川と合流させて、南北の勢いを相殺させ、東の高岩へと流れを向けます。
6.天然の岸壁である高岩に釜無川をぶつけて、流れを跳ね返らせて、南に転じさせます。
7.御勅使川南流を合流させ、高岩から跳ね返ってきた釜無川の流れを整えます。
8.龍王川除や霞堤を築いて、洪水が起こった場合でも、遊水池に逃がせるようにします。
このような大規模な治水コントロールシステムですが、現在、信玄堤の御勅使川沿いの治水施設は、明治時代以降の治水事業によって、その機能は果たしていません。しかし、飛行機も土木機械もなかった戦国時代において、川の流路を変えてまで甲府の町を守ったその技術や考え方は、現在の防災においても役立つことがあるかもしれません。
洪水氾濫シミュレーションは、地形や流量などの設定を変えて、何度も実験をすることができるコンピュータシミュレーションです。近年では、ハザードマップの作成などにも活用されています。本講義では、洪水氾濫シミュレーションの結果を見ながら、信玄堤の各治水施設群の治水能力を確認しつつ、信玄の行った治水事業と現在の防災について考えてみましょう。
講師:東京都立大学 学術情報基盤センター 特任准教授 根元 裕樹








