
鎌倉時代後期、1274年と1281年の二度にわたり
元(モンゴル)軍が日本に侵攻した「蒙古襲来(元寇)」。
二度目の「弘安の役」で九州北部に攻め込んだ元軍の船団は
暴風雨に見舞われたことにより壊滅し、蒙古襲来は終焉を迎えました。
それから730年の時を経て、
鷹島(長崎県松浦市)の南海岸の海域から、
元軍の沈没船が発見されたのです。
ここから明らかになった、新たな史実とは。
調査研究チームを率いてこの快挙を成し遂げた池田教授に、
「水中考古学」の魅力と、その可能性について伺いました。


國學院大學 研究開発推進機構 教授
池田 榮史
1955年、熊本県天草市生まれ。國學院大學に入学後、自身と同じ熊本県出身の考古学者・乙益重隆教授に師事。國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻(考古学系)博士課程前期修了。琉球大学国際地域創造学部教授を経て2021年より現職。文化庁水中遺跡調査検討委員会委員長も務める。
1955年、熊本県天草市生まれ。國學院大學に入学後、自身と同じ熊本県出身の考古学者・乙益重隆教授に師事。國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻(考古学系)博士課程前期修了。琉球大学国際地域創造学部教授を経て2021年より現職。文化庁水中遺跡調査検討委員会委員長も務める。

「水中考古学」とは、どのような学問なのでしょうか?
池田教授: 海底や湖底、川底など水中に沈んだ遺跡や遺物を調査研究するのが「水中考古学」です。潜水機器の発達に伴い、ヨーロッパでは1950年代から水中での発掘調査が行われれるようになり、日本ではようやく1970年代になって、北海道・江差港沖に沈む幕末の軍艦「開陽丸」の調査を皮切りに本格的な発掘調査が始まりました。しかし、日本全国で現在確認されている遺跡数をみると、地上は約47万件あるのに対し、水中はまだ400件弱。水中考古学はこれからの調査研究への期待が高まる分野といえるでしょう。水底に眠っている遺跡・遺物は、意外と保存状態が良いのです。例えば、木材を喰い尽くすフナクイムシという貝類がいますが、これが生息できない海底の泥の中であれば、木造船や漆器、衣服といった陸上では土壌の影響を受けて劣化しやすい有機質のモノも残りやすい。銅銭などの銅製品もきれいに残っています。
鷹島と海底発掘調査との関わりについて教えてください。
池田教授: 「蒙古襲来終焉の島」として知られる鷹島は、九州北部の伊万里湾に浮かぶ小さな島です。1281年の「弘安の役」では元軍の大船団4400艘が鷹島沖に押し寄せましたが、暴風雨により壊滅的な打撃を受け、その多くが沈んだとされています。この戦いの舞台となった鷹島では、元軍の船のモノと思われる碇石や壺類が漁網に引っかかるなどして、昔から揚がっていました。さらに地元住民の方が浜辺で採取した銅の印鑑を調査したところ、元軍の部隊長が持つ「管軍総把印(かんぐんそうはいん)」であると判明し、鷹島一帯は蒙古襲来の遺跡だということがより明確になってきました。こうして鷹島沖を含む「鷹島海底遺跡」では、1980年代から断続的に調査が行われるようになったのです。
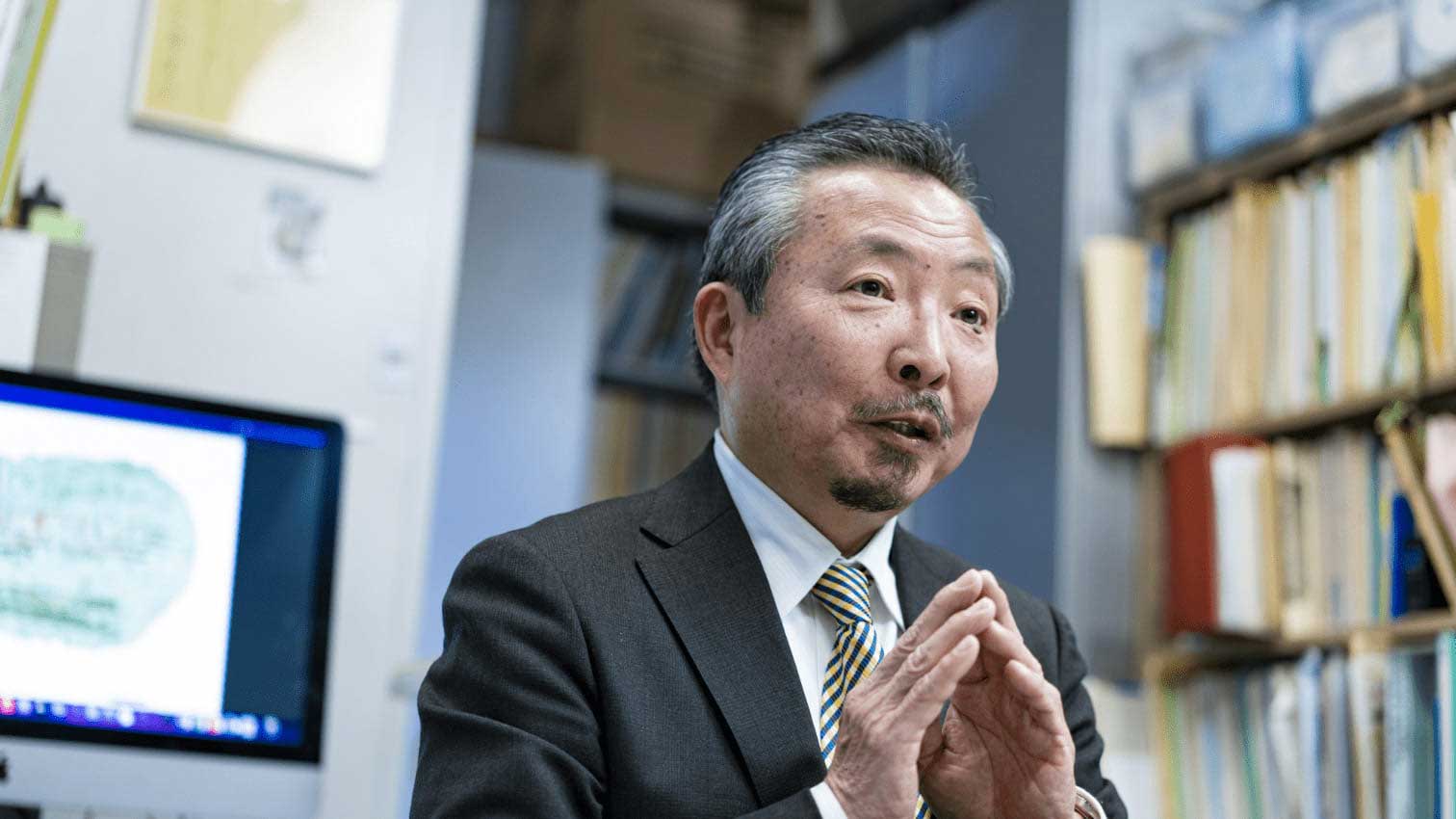
池田教授のチームが進めてきた「鷹島海底遺跡」での調査研究プロジェクトについて教えてください。
池田教授: 従来の調査では、蒙古襲来の全体像がなかなか見えてきませんでした。そこで蒙古襲来の痕跡はどのような形で海底に残っているのか、その全容の解明に挑むべく、私たちのチームは国の科学研究費の助成を受けた学術調査を2006年から2021年まで実施しました。プロジェクトは大きく分けて、「海底の地形・地層図作成」「発掘」「保存」という3つのプロセスで進みました。まず、海底資源調査の専門家の協力のもと6年をかけて、音波探査機を使った伊万里湾海底の地形および地層図をつくりました。ここで得られたデータを分析した結果、海底に露出したまま残っている元軍の沈没船は無いと分かったのです。では、船が今も残っているとしたら、どこにあるのか。それは冒頭に出てきたフナクイムシに喰い荒らされない場所、つまり密封状態で生物が生息できない、海底に堆積した泥土層の中しかありません。そこで音波探査で出てきた海底堆積土層反応の中から沈没船が眠る可能性がある場所をピンポイントで特定した上で、海底での発掘調査を始めたのです。
海底での発掘調査は、陸上で行うものよりもかなり困難が伴うかと思いますが。
池田教授: 海底では、陸上のようにスコップや移植ゴテで掘ることはなく、海水を流し込んで泥や砂を横移動させる水中ドレッジという器具を使います。ダイバーが潜水して作業できる時間は、水深20メートルで1回30分程度。潜水病にも注意する必要があるので、休憩も入れたら一人あたり1日にできる作業は1時間が限度です。さらに水中スクーターを使って海中の濁りを取っていても、作業中は泥砂で視界が遮られ、水中眼鏡のすぐ先もほとんど見えません。限られた時間内で手探りをしながら、石だろうか……、板だろうか……、そもそも本当にあるんだろうか……と時に不安になりながら、手の感覚を頼りに少しずつ掘り下げていきました。

沈没船の調査風景。水中ドレッジを使いながら、少しずつ掘り下げを進めた。
こうした苦労の末に、ようやく発見に至ったのですね。
池田教授: 2011年10月、水深約23メートル、海底を1メートルほど掘り下げた位置で、船底中央の木材にあたる竜骨と船底材の外板を発見し、元軍の船がほぼ原形を留める形で残っていることを確認しました。さらに音波探査で1艘目と同じような反応があった別の場所を掘り下げていくと、2014年には2艘目の沈没船の発見につながりました。1艘目の発見ののち「鷹島海底遺跡」は海底遺跡では初となる国指定史跡となり、鷹島は水中考古学において日本を代表する事例として国内外から注目を集めるようになりました。ただ、ここで少し強調したいのは、今回の発見は偶然ではないということです。音波探査でデータを集めて分析し、試行錯誤を繰り返した末に船に辿りついた。これはまさに科学的な実験のプロセスそのものであり、こうしたプロセスがあるからこそ、水中考古学はトレジャーハンティングではなく、学問にほかならないという証しなのです。
その後の調査研究では、どのような成果が出ているのでしょうか?
池田教授: これまでの成果の一つに「てつはう(てっぽう)」があります。教科書でおなじみの『蒙古襲来絵詞』でも、元軍と鎌倉武士の戦いの最中に「てつはう」がさく裂する場面が描かれています。この実物とみられる直径15センチ前後の焼物が、鷹島の船からも出てきました。研究者によっては「てつはう」を「馬脅し程度」とみる向きもあったのですが、そのうちの一つをX線CTスキャン装置で解析したところ、内部には鉄や陶磁器の破片が詰め込まれており、火薬で爆発させたら武器として高い殺傷能力がある可能性が濃厚になってきました。これは史実を裏付ける成果といえるでしょう。また、2022年にはクラウドファンディングで募った資金により大型の木製椗の引き揚げが実現し、この調査と保存処理作業も進む予定です。

海底での発掘調査では、池田教授もダイバーの一人として潜る。
発見後、船本体は埋め戻されて現地保存されていますね。今後は船体の引き揚げを進めるのでしょうか?
池田教授: 泥の中でしっかりとパッケージされていたおかげで残っていた元軍の船を、海底で掘ったままにしておけば当然劣化してしまいます。しかし引き揚げるとなると、それはそれで資金が必要となります。そこで現時点では、海水や酸素、フナクイムシが入り込まないための適切な保存処理方法の研究を重ねた上で、発見した2艘共に海底に埋め戻して保存しています。ただ将来的には、今後発見される沈没船を含めた引き揚げを視野に入れています。今見つかっているのはたった2艘。もし仮に、文献史料で伝わる通り4400艘もの船が沈んでいるとしたら、ほんの一部ですよね。だからもう少し多くの船を探し出して大きさや構造を複数パターン把握し、船体の選択肢を増やした上で、引き揚げにつなげていきたいと考えています。
日本の「水中考古学」は、これからどのように発展していくとお考えですか?
池田教授: ヨーロッパで始まった水中考古学は今、アジア地域で関心が高まりつつあります。自分たちの地域の海底にはどのような遺跡や文化財があり、それらをどのように把握して次代に伝えていくのか。その模索が始まっているのです。日本では鷹島が水中考古学をリードし、調査方法から保存処理方法まで、数多くのノウハウを蓄積してきました。そこで鷹島が今後、日本だけでなくアジア地域全体の水中遺跡・文化財の保全・調査に関するシンクタンクとなっていくことが、大いに期待されています。

最後に、高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
池田教授: 皆さんは今、高校でいろいろな科目を学んでいると思います。もしかしたら文系の高校生の場合、数学や物理はちょっと……という方もいるかもしれません。でも、入試というハードルを越え、晴れて大学で自分の好きな分野を探究するという時に、数学、物理、生物、英語など、これまでの蓄積が活きてくる場面が数多くあります。実はそれは、水中考古学を研究する中で私自身が実感していることなのです。例えば、音波探査では地球物理学や地質学が、ダイバーとして潜る時には生物学の知識が、文献を調べる上では英語や中国語も必要となります。大学入試というハードルを越えることだけを目標とせずに、その先の未来を見据えて、まずは頑張ってください。皆さんとお会いできることを、楽しみに待っています!

池田教授は書籍も多数執筆しています。水中考古学をテーマとした『海底に眠る蒙古襲来 水中考古学の挑戦』(吉川弘文館)、『元軍船の発見 鷹島海底遺跡』(新泉社)のほか、沖縄の戦跡考古学を紐解く『沖縄戦の発掘 沖縄陸軍病院南風原壕群』(新泉社)なども。興味がある方は、図書館や書店でぜひご覧ください。





