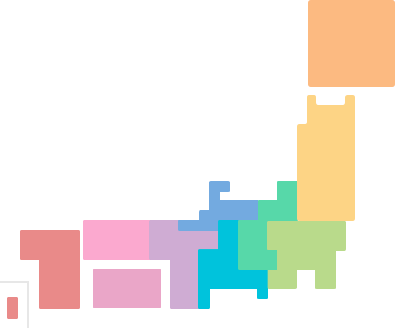考古学とはどんな学問?
考古学とはどんな学問?
ヒントと答えはすべて地中に
中学や高校の社会の授業で、旧石器時代や縄文時代の人々の暮らしぶりを学習したと思いますが、文字のない時代のことですから、手掛かりは遺跡から出土した遺物以外にいっさいありません。ヒントと答えはすべて地中にあるのです。そこで彼らが生活した場所(遺跡)を発掘調査します。こうした学問を考古学といいます。
考古学と他の学問とのかかわり
自分に合った分野を選ぶことが大切
考古学には歴史学や文化人類学、自然人類学、文化財科学など、類似する学問がいくつかあります。大学選びにおいてはそうした学問との違いを理解したうえで、自分に合った分野を選ぶことが大切でしょう。またテクノロジーの進化によってこれまでわからなかった事実がより詳細に判明するようになっています。現在の考古学はこうした領域間をまたぐような研究も盛んに行われています。
考古学では何をどのように学ぶか
実習を通して発掘調査の技術を身につける
考古学を学べる学科としては、「歴史学科」「史学科」「文化財学科」「歴史遺産学科」などがあります。これらの学科では、考古学の歴史や国内外の地域史を学びながら、実習を通して発掘調査の技術を身につけるというのが一般的です。
考古学はこんな人に向いている
発掘調査の仕事に就く先輩も
意外と知られていませんが、国内では毎年約9000件の発掘調査が行われており、学生時代に身につけた調査技術を生かして、発掘調査の仕事に就く先輩もいます。また学芸員として文化財の保護・活用に携わるという選択肢もあります。
考古学を学んだ後の進路と今後の展望
さまざまな学問領域への興味も必要
考古学を学ぶうえでは、歴史に関心があることはもちろん、さまざまな学問領域への興味も必要になります。さらに発掘調査には忍耐強さやチームワークが欠かせません。また、発掘後には小さな破片をつなぎ合わせて修復することから、細やかさも求められます。
考古学の先生にきく
考古学ではこんな研究をしています
古代エジプト文明の真相を探る
私が専門とするのは、古代エジプト文明。ピラミッドやツタンカーメン王の黄金のマスクなどに代表される、とてもユニークな文化を築いた文明です。研究するうえでは発掘調査によって発見されたミイラや生活道具、美術品、さらに文字による記録を手がかりにして、歴史の真相を探ります。(駒澤大学 文学部歴史学科 外国史専攻 大城道則教授)
人々の暮らしを物語る遺物はすべて研究対象
縄文時代が私の テーマです。その時代に生きた人々がどんな暮らしぶりだったのか、どんな社会であったのかを研究しています。人の骨や土器や石器、どんぐりの実や魚の骨といった食べ物など、当時の人々の暮らしを物語る遺物はすべて研究対象になります。また研究の成果はわかりやすく、合理的に説明することが大切です。複雑な難問も最後には美しく解ける数式のように説明したいと心がけています。(明治大学 文学部 史学地理学科考古学専攻 阿部芳郎教授)
考古学のここが面白い
新たな遺跡が発掘されれば大発見!というロマン
新たな遺跡が発掘されれば大発見!というロマンがあるのが考古学。なかでも古代エジプト文明には、ピラミッドはなぜ造られたのか、ツタンカーメン王はなぜ死んだのかなど、研究しがいのある謎が多い地域ですね。(駒澤大学 文学部歴史学科 外国史専攻 大城道則教授)
骨や石や木などのさまざまな遺物から想像力を働かせる
縄文時代には文字がありません。ですから、文献も残されていません。したがって、当時の様子を知るのに、記録を頼りにすることはできません。 そこで、土の中から出てきた骨や石や木などのさまざまな遺物を分析し、そこから想像力を働かせていくのですが、それこそが考古学の醍醐味です。科学の進歩とともに化学や数学といった理系分野との学際研究が著しく進んでおり、その結果、さまざまな新しい発見によって定説が覆されるというのも珍しくありません。(明治大学 文学部 史学地理学科 考古学専攻 阿部芳郎教授)
考古学の学生にきく
考古学を選んだ理由を教えて!
- 考古学でしか解明できないことがおもしろそうだと思った。
- 遺物からさまざまなことを読み取れる学問に興味があった。
- 発掘を実際に体験してみたかった。
高校でさまざまな歴史を学んでいくうちに、日本史に最も興味が湧きました。進路を考えていたころ、考古学でしか解明できないことがあることを知り、深く研究してみたい!と思ったからです。
(人文社会科学部 人文社会科学科 あさん)
文字情報がなくても、土器や石器などからはさまざまなことが解明できると知りました。過去の遺物からどのようなことが読み取れるのかを実際に学んでみたいと思ったからです。
(文学部 史学地理学科 さといださん)
もともと考古学や発掘調査に興味がありました。発掘がどのように行われているのか、実際に体験してみたいという気持ちが強かったからです。
(文学部 歴史学科 宇響さん)
歴史アニメが好きで世界史にも興味をもつようになり、深く研究してみたいと思ったからです。
(文学部 史学科 りんごさん)
時間割と授業内容を教えて!
キャンパスライフの参考に、文学部歴史学科2年生の時間割をのぞいてみましょう。
日本史や世界史を中心に、英語や日本の憲法などについても幅広く学びます。
1年次には新入生セミナーや日本史概説など大まかに学問全体を理解するための授業が多く用意されています。2年次以降は歴史区分などでコースに分かれて詳しい勉強を始めます。史料講読を学ぶことで自ら歴史を考えて構築していく授業などがあります。
3年次はひきつづき基礎的な学問と並行して専門分野の学びを深めます。4年次では卒業論文の執筆を行います。授業を受けながら自身の研究にも取り組みます。
考古学ではこんなテーマで学べるよ!
- 特定の時代や、地域についての深い歴史。
- 土器など歴史的資料からの調査・研究。
- 遺跡の発掘や出土品の分析など実地研究。
日本考古学を学んでいます。テーマは、奈良時代から平安時代までの東北地方です。この時代の東北地方は、太古のロマンが感じられる遺物もたくさんあり、知れば知るほど興味が湧いてきます。
(人文社会科学部 人文社会科学科 あさん)
1851年のロンドン万国博覧会について研究しています。イギリスの歴史や階級社会とも関連づけながら、卒論を作成していきたいと考えています。
(文学部 史学科 りんごさん)
私の研究テーマは、古墳時代に生産された須恵器です。土器は地域によって特徴もさまざまで、探究心が常に刺激されています。
(文学部 史学地理学科 さといださん)
遺跡の発掘と出土品の分析をしています。実際の出土品を使って、模様や形を紙に写し取る作業を行ったり、出土品を図化する方法を学んでいます。考古学を学ぶうえでは、マスターしなければならないとても重要な作業です。
(文学部 史学地理学科 匿名希望)

考古学で楽しかった演習やテーマを教えて!
- 「考古学」にも「科学」は重要!?
- 「博物館演習」で自分が考えた企画を展示。
- 土器で炊飯にチャレンジしたのは一生の思い出。
「自然科学」と「考古学」の授業が新鮮で興味深かったです。考古学は歴史だから文系と思っていましたが、遺物を良い状態で保存するためには科学的な手法が用いられるなど、理系の要素もあると知って驚きました。
(文学部 史学地理学科 さといださん)
学芸員の資格を取得するために博物館演習に参加しました。今まで展示は見るだけだったのですが、実際に展示の内容や企画を考えたりしたことは、とても貴重な経験になりました。
(文学部 史学科 りんごさん)
「実験考古学」という授業での体験が思い出に残っています。現在では炊飯器で簡単にご飯が炊けますが、授業では弥生時代の方法を使ってご飯を炊くことにチャレンジしました。できあがった時の感動とその味は忘れられません!
(人文社会科学部 人文社会科学科 あさん)
考古学を学んでみてどうだった?
- 歴史を考えることは未来につながっていると気づいた。
- 地理学、科学、文学… 幅広い知識が必要な学問。
- さまざまな角度から深く追究していく癖がついた。
過去の歴史を考えることが私たちの未来につながっていくと気づきました。教訓は過去からしか学べません。教科書を否定するような説を考えたりしたことで、より広い視野で歴史を見ることができるようになりました。
(文学部 歴史学科 宇響さん)
入学前は、考古学に科学的な要素があるとは思っていませんでした。しかし、地理学とも関連しているなど、考古学には幅広い分野の知識が必要です。遺物からは多くの情報を読み取れますが、着眼点によって得られる成果は大きく異なることに気づきました。
(文学部 史学地理学科 さといださん)
歴史は繰り返すということを改めて考えました。社会に出ても常に学ぶ姿勢は大切にしていきたいと思います。
(文学部 史学科 りんごさん)
記事はスタディサプリ編集部が考古学を学ぶ学生に対して独自に行ったアンケートへの回答をもとに構成しており、実際の履修内容は各学校により異なる場合があります。各学校についての詳細な情報は学校ページにてご確認ください。
もっと在校生たちに聞いてみよう

様々な学修や活動を通して広く知識を身につけ、「できること」を増やしていきたい
郡山女子大学短期大学部 地域創成学科
Yさん

文化財を守り、今後の活用方法まで考えられる学芸員を目指しています
鶴見大学 文学部 文化財学科
竹崎 一生さん

大学生活の中で授業時間が一番好き!常に歴史のことを考える日々です
奈良大学 文学部 史学科
竹内 翼さん
全国のオススメの学校
-
弘前大学(人文社会科学部)国公立大学/青森
-
 徳島文理大学(文化財学科)高松駅横へ2025年4月移転の香川キャンパス!最新の「都市型キャンパス」で学べる私立大学/徳島・香川
徳島文理大学(文化財学科)高松駅横へ2025年4月移転の香川キャンパス!最新の「都市型キャンパス」で学べる私立大学/徳島・香川 -
 大東文化大学(歴史文化学科)「真ん中に文化がある」 地域・領域・時代を超えた多彩な文化が交差し、出会う場へ私立大学/東京・埼玉
大東文化大学(歴史文化学科)「真ん中に文化がある」 地域・領域・時代を超えた多彩な文化が交差し、出会う場へ私立大学/東京・埼玉 -
富山大学(人文学部)国公立大学/富山
-
 天理大学(歴史文化学科)社会に貢献できる学びを15学科に進化させ、新生・天理大学をスタートします。私立大学/奈良
天理大学(歴史文化学科)社会に貢献できる学びを15学科に進化させ、新生・天理大学をスタートします。私立大学/奈良 -
 駒沢女子大学(国際日本学科(仮称))2025年4月、共創文化学部・観光文化学部・空間デザイン学部を開設予定(構想中)私立大学/東京
駒沢女子大学(国際日本学科(仮称))2025年4月、共創文化学部・観光文化学部・空間デザイン学部を開設予定(構想中)私立大学/東京 -
 郡山女子大学短期大学部(地域創成学科)教養を備え、自主・自立できる心豊かな女性を目指します私立短大/福島
郡山女子大学短期大学部(地域創成学科)教養を備え、自主・自立できる心豊かな女性を目指します私立短大/福島 -
 東海大学(人文学科)学びの領域を広げ、より専門性の高い学びを追究し、新時代の社会を創造する場所へ!私立大学/神奈川・北海道・東京・静岡・熊本
東海大学(人文学科)学びの領域を広げ、より専門性の高い学びを追究し、新時代の社会を創造する場所へ!私立大学/神奈川・北海道・東京・静岡・熊本 -
 立正大学(文化遺産・芸術コース)開校150年以上の歴史と伝統。主体的な学びで個性あふれる人間力を育む。私立大学/東京・埼玉
立正大学(文化遺産・芸術コース)開校150年以上の歴史と伝統。主体的な学びで個性あふれる人間力を育む。私立大学/東京・埼玉 -
 福岡大学(人文学部)9学部31学科、在学生約20,000人が、広大なひとつのキャンパスで学ぶ総合大学。私立大学/福岡
福岡大学(人文学部)9学部31学科、在学生約20,000人が、広大なひとつのキャンパスで学ぶ総合大学。私立大学/福岡