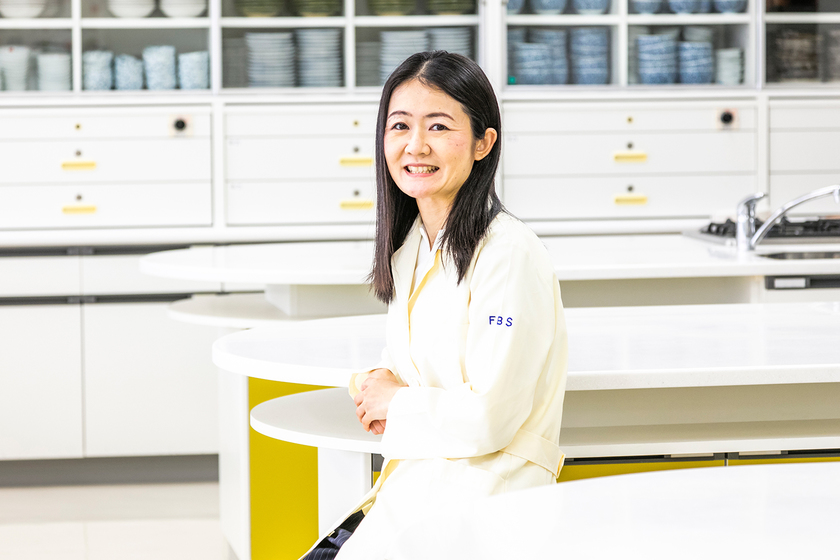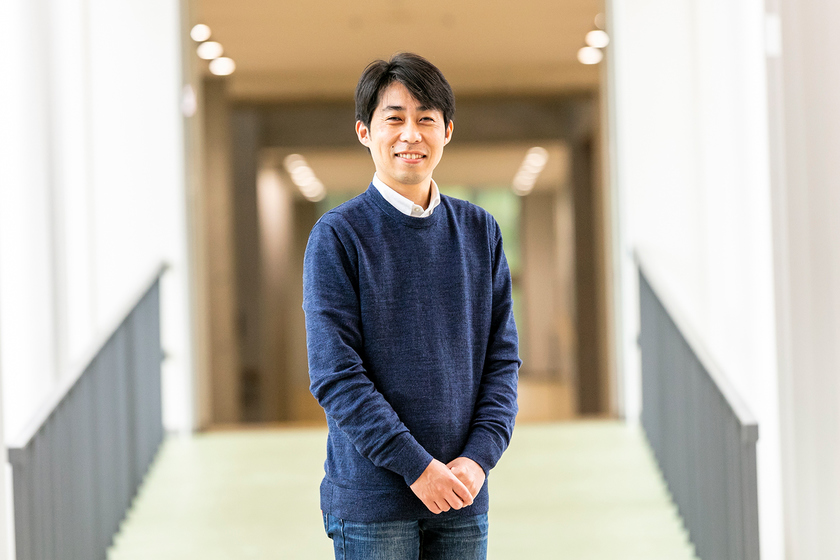スペシャル学校情報
日本大学 生物資源科学部
- 定員数:
- 1520人 (2024年度)
生物資源科学部はこれからの時代を見据えて新たな学科体制でスタートしました
| 学べる学問 |
|
|---|---|
| 目指せる仕事 |
|
| 初年度納入金: | 2024年度納入金 138万円~241万円 (諸会費等別途) |
|---|
日本大学 生物資源科学部の募集学科・コース
バイオテクノロジーを用いて生命活動を解明し、深刻化する社会問題を解決していきます
動物のさまざまな潜在能力、生体機能を学び、人類の文化的生活への応用を考えます
海洋生物や棲息環境に関する知識と技術を応用し、海洋資源の活用と人のくらしの調和を創造します
森林を多角的に研究し、持続可能な社会に役立つ森林の働きを学びます
地球規模で発生している環境問題の解決方法や自然環境の保全について学びます
生命科学の知識と先端技術を修得し、それらを応用して食料生産やフラワーコーディネートのスペシャリストへ
人の健康の維持・増進に役立ち、安全な新食品を開発する力を養います
「食」に関わるさまざまな課題を掘り下げ、社会で活躍できる「食をプロデュースする人材」を育てます
多様化時代の生物資源・環境と人の共生を多角的な視点からマネジメントします
獣医師と協働して動物の健康と福祉に貢献する愛玩動物看護師を養成します
最先端の動物医療を通して、動物の健康と公衆衛生に貢献する獣医師を育成します
日本大学 生物資源科学部のキャンパスライフShot

- 犬のモデルを使用した内科学的検査を実施している様子。

- 抗菌ペプチド(ガセリシン)の生産遺伝子群を導入した乳酸菌の塗末培養。

- 植物の栽培技術や管理方法を体得する実習でトマトの剪定。
日本大学 生物資源科学部の学部の特長
生物資源科学部の学ぶ内容
- 生物資源科学部
- 動物、植物、微生物とそれらに由来するあらゆる生物資源を対象に、「生命」「食料」「資源」「環境」に関する教育・研究を展開していきます。
生物資源科学部の先生
-
point こんな先生・教授から学べます
事実を暗記し、ただ実験を繰り返すより、その背景にある意味を理解すれば、学びは遙かに面白くなります。
少しでも植物のすばらしさに興味を持ってもらいたいという伊藤先生。講義の進め方としては、ただの事実を教えるだけではなく、どのような実験の積み重ねで、この事実が判明したかという経緯も説明。学生に追体験させることで、研究の面白さや考察の大切さが理解できるよう心がけているそうです。卒研な…

-
point こんな先生・教授から学べます
学生実験は実際に手を動かし、自分で結果を出してみることが、面白さを知る秘訣だと思います。
相澤先生が担当する講義では、マクロの視点と同様にミクロの視点も重要なので、日常の話題に置き換えて解説するなど、興味を持って聞いてもらえるよう工夫しているそうです。また学生実験のメニューは、研究室に入ってから実際に用いる実験手法を多く取り入れ、取り組む学生には実験の面白さに気づいて…

-
point こんな先生・教授から学べます
実習や研究室での学びを通じ、他の仲間と協力して成果を上げる力、それを表現する力を磨いてほしい。
串田先生は「実習科目においては、みんなでどのように協力し、成果を上げていくか、そういった力をつけることが教育上の大きな目標となっている」といいます。一方、研究室の学びでは、興味を持ったことを探求する仕方と、それを他人に伝える表現力やプレゼンテーションの力を重視しています。こうした…

-
point こんな先生・教授から学べます
実習ではきのこや虫など、自分で興味のあるものを自分で探し、そこから学びを深めてもらいます。
学生には現場で実物をみて学んでもらいたいという太田先生。実習では、自分で採取したきのこやサンプルを観察、分離し、標本を作成させています。授業でも病害や腐朽材の実物サンプルを回覧し、触ってもらうこともあります。また卒業研究は、自分で一つの研究テーマを決めるところからスタートします。…

-
point こんな先生・教授から学べます
地域でのプロジェクトや食品会社とのコラボなど、学びを社会で実践できる機会を広く用意しています。
谷米先生のもとには、将来食に関する仕事がしたいという学生が多数やってきます。そこで学生には、座学で学んだ知識を実習や演習で実践できるような機会をできるだけ用意するようにしています。例えば、藤沢産キノアを広めるプロジェクトで、レシピ開発や販売、マーケティングなどを経験してもらうのも…

-
point こんな先生・教授から学べます
授業では香りを体験することで、感覚的な情報と科学的な知識を結びつけ、より深い理解へと導いています。
大畑先生が担当する授業の1つでは、香りを嗅いで感覚的に理解することを大切にしているそうです。その日の授業内容に関連する香料、例えばリンゴの香りや醤油の香りなどを、ムエットと呼ばれる匂い紙につけて学生に配布し、香りを存分に嗅いでもらいます。香りの特徴や印象などの感覚的な情報を体験す…

-
point こんな先生・教授から学べます
ネット上にはない、新しいものを見つける・作る楽しさを、授業や実習を通じて感じてください。
大学の学びは、自分自身で体験し、物事を考えることこそが本当に重要であるという東先生。実習では種を播くところから収穫するまで、すべての管理を学生自身に任せています。熱心に観察すると栽培管理のちょっとした違いで、植物は明らかに違う姿になることがわかりますし、植物種によっては教科書とは…

-
point こんな先生・教授から学べます
自分で考え、自分で解決できる力を身につけてもらえるよう、授業でも研究でも自主性を重んじています。
最近の学生は、与えられた課題をこなす能力は非常に高い。その上でさらに、自分で考え、探究心を持って自分で解決できる力も身につけてほしいと枝村先生は考えています。ですから授業や実習では、一方的に話すのではなく、双方向的に考えを問うような形で展開することを心がけています。卒論などの研究…

-
point こんな先生・教授から学べます
教室で理論を学び、現場に出てのリアルな声に触れることで、高い問題意識を持つ。
講義や実習などでは、なぜ学ぶ必要があるのか、学んだことをどこに活かせるのか、学生が自身に問い続け明確にできるよう、日々時事的な事柄や学生が興味を持ちそうな話題を積極的に組み込んでいます。また、国際化時代における食と農に関する市場動向の分析、経営学理論の学習、フィールドリサーチを通…

-
point こんな先生・教授から学べます
研究室のフィールドワークでは、神奈川の海はもちろん、西表島や沖縄などにも足を伸ばしています。
授業では頭を使って考えることを重視するという糸井先生。今はインターネットなどを使い、知識自体は簡単に得られます。大切なのは得た知識をどのように組み合わせていくか。授業中にはその点をとくに考えさせるようにしています。研究では、江の島などへサンプルの採取によく出かけているそう。また、…

-
point こんな先生・教授から学べます
授業でも研究でも、学生自らの気づきや自由な発想を大切にし、そのためのサポートを行っています。
人の役に立つ微生物について、その魅力をさまざまな角度から伝えたいと願っている上田先生。授業では個々の微生物の話であっても、それらが徐々に学生の頭の中で繋がるように筋道を立てて話し、「なるほど、そういうことか」と、学生自ら気づけるような講義の体系にしたいと考えているそうです。一方研…

生物資源科学部の卒業生
-
point 先輩の仕事紹介
大学での学びを生かし、分析の仕事を通じて、製品開発に貢献しています。
神奈川県川崎市にある研究所で、「評価・分析室 構造解析グループ」という部署に所属しています。ここには調味料や冷凍食品、医療品や電子材料に至るまで、さまざまな部署から分析案件が舞い込みます。例えば食品であれば"おいしさ"を構成する成分がどのくらい入っているか、開発中の製品がデザイン…

-
point 先輩の仕事紹介
農家の声に耳を傾け、農家に信頼される農業普及員になりたい。
大学卒業後、千葉県に農業職として入庁。現在は茂原市にある長生農業事務所に勤務しています。改良普及課では、直接農家の方に接しながら、技術指導や就農支援を行っています。また、地域に適した新しい技術の導入を提案し、支援などもしています。私自身は、主に大学でも研究したイチゴ及び花き全般を…

-
point 先輩の仕事紹介
大学時代に挑戦し経験したことは、今の自分を形作る大切な土壌となっています。
入社後2年間営業を務めた後、昨年までRTDマーケティング部に所属し、缶チューハイなどのマーケティングを担当していました。そこで大きな経験となったのは、初めて自分から手を挙げ、新しい缶チューハイの商品開発を任せていただいたことです。やりがいはありましたが、商品をゼロから立ち上げる産…

-
point 先輩の仕事紹介
動物の“ホームドクター”として、地域の方々の人生と共に歩んでいきたい。
日大の大学院へ進学し、博士課程修了後、横浜市内に現在のコルフェ動物病院を開業しました。開業医になって最初に悩んだのは、どうしたら飼い主さんが満足する医療を提供できるかという点です。飼い主さんにはそれぞれ時間的、経済的な制約もあり、大学病院のようにすべての必要な治療を施せるとは限り…

-
point 先輩の仕事紹介
大学以来続けているトマトの研究で、農家のお役に立てることが大きな目標です。
神奈川県平塚市にある県の農業技術センターで、農産物の品質評価などに携わっています。主に担当している作物は、大学の研究室以来付き合いの長いトマトとなります。県で開発された「湘南ポモロン」は、リコペンなどの機能性成分がたっぷり含まれている品種で、当センターの普及指導部などとも協力し、…

-
point 先輩の仕事紹介
食品メーカーで働く夢が叶い充実した毎日。次は海外へ日本のものづくりを伝えたい。
マヨネーズなどを生産する工場の品質保障課で、食品の安全な生産や管理方法を定める仕事などを担当しています。私は高校時代から食品メーカーに勤めることが夢で、大学も食や健康について学べるかどうかという視点で選びました。卒業後は大学院に進学し、研究職をめざすことも考えましたのですが、以前…

-
point 先輩の仕事紹介
イルカも自分自身もトレーニングを積み、お客様を虜にするショーを演じたい。
神奈川県藤沢市にある新江ノ島水族館の飼育員として、イルカなど海獣類の飼育に携わっています。業務内容は多岐にわたり、日常的な給餌や健康管理などはもちろん、イルカショーに必要なトレーニングや、「イルカのおにいさん」としてショーへの出演も行っています。言葉が通じない動物とのトレーニング…

-
point 先輩の仕事紹介
ファンケルのサプリメントといえばこれ!そんな製品を自分の研究から生み出したい。
株式会社ファンケルの横浜にあるヘルスサイエンス研究センターに勤務し、バイオサイエンスや健康食品に関する基礎研究に携わっています。当社は、化粧品や健康食品などについて研究から開発、製造、販売まで一貫して行っており、基礎研究の時点からお客様に寄り添ったものづくりを意識して日々業務にあ…

生物資源科学部の設立の背景
- 2023年4月、新学科体制スタート
- 社会の変化に伴う「生命」「食料」「資源」「環境」の諸問題を解決するためには、新たな視点から教育・研究に取り組み、さらに最先端の知識・技術とSDGsやOne Healthの意識をもって対応できる人材養成が急務となります。これからの時代を見据えて構成を大きく見直し、9つの学科を新しく設置して全11学科の構成で新たな生物資源科学部としてスタートしました。
生物資源科学部の教育目標
- 生命・食料・資源・環境をつなぐ人材養成
- 私たちのくらしに重要な生命・食料・資源・環境の課題を複眼的に捉え、自ら解決できる「実践力」のある人材を養成します。
日本大学 生物資源科学部の入試・出願
日本大学 生物資源科学部の目指せる仕事
日本大学 生物資源科学部の就職率・卒業後の進路
■2023年3月卒業生就職実績
カネコ種苗、前田建設、アサヒ飲料、赤城乳業、山崎製パン、キユーピー、マルハニチロ、丸大食品、日清オイリオグループ、フジパングループ本社、森永乳業、伊藤園、長谷川香料、アイリスオーヤマ、大王製紙、イオンリテール、星野リゾート、江ノ島マリンコーポレーション、全国農業協同組合連合会、日本中央競馬会、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、東京都庁、警視庁、神奈川県庁、埼玉県庁、横浜市役所、東京都特別区 ほか
■大学院進学
大学院に進学し、専門性の高い研究を続ける卒業生もいます。併設されている大学院では、5専攻からなる生物資源科学研究科と獣医学研究科において、先端的な応用研究が行われています。